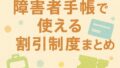こんなお悩みありませんか?
- 福祉の仕事に興味があるけど、実際どんなことをするのか分からない
- 「やりがいのある仕事」って聞くけど、大変なことはないの?
- 福祉系の資格を取りたいけど、どれを選べばいいか迷っている
この記事で分かること
✅ 福祉の仕事の実際の現場での様子
✅ 4つの国家資格それぞれの特徴と働く場所
✅ 理想と現実のギャップ、そして本当のやりがい
このブログを初めて読む方は、まず運営者プロフィールをご覧ください。
→ 【はじめまして】福祉のプロ×当事者が始める理由

この記事を書いている人☺
社会福祉士・介護福祉士・保育士・精神保健福祉士の4つの国家資格を持ち、高齢者・児童・障害者ので現場経験があるバッキーが、教科書には書かれていない福祉の仕事の「リアル」をお伝えします。
📂 カテゴリー別記事一覧
🏛️ 社会保障制度 | 💼 福祉のお仕事 | 🧠 障害と生きづらさ
※本記事は社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・保育士の資格を持つ私の実体験や専門知識、福祉制度の理解に基づく情報提供です。医学的診断や治療の代替となるものではありません。
1. 【基本編】福祉の仕事とは?中学生でも分かる基礎知識
簡単に言うと、福祉の仕事は「困っている人を支える仕事」です
福祉の仕事を一言で表すなら、
**「様々な困りごとを抱えた人たちの生活を、専門知識を使って支援する仕事」**です。
対象となる人は:
- 高齢者(お年寄り)
- 子どもや子育て中の家族
- 障害のある人
- 生活に困っている人
- 病気やケガで支援が必要な人
なぜこの仕事が必要なの?
昔は家族や近所の人が助け合って生活していましたが、現代では一人暮らしの高齢者が増えたり、核家族化が進んだりして、専門的な支援が必要な場面が増えています。
そこで、専門知識と技術を身につけた人が、困っている人を支援するのが福祉の仕事です。
どんな場所で働くの?
- 特別養護老人ホーム、デイサービス(高齢者分野)
- 保育園、児童福祉施設、学校(児童分野)
- 障害者支援施設、グループホーム(障害者分野)
- 病院、市役所、社会福祉協議会など
2. 【詳細編】4つの国家資格の具体的な内容
福祉の国家資格について詳しく見ていく前に、障害福祉分野で活躍する国家資格の全体像を知りたい方は、
[障害福祉を支える国家資格一覧!あなたに合った資格がわかる完全ガイド]で体系的にまとめています。」
ステップ1:社会福祉士(ソーシャルワーカー)
何をする人?
- 生活の困りごと全般の相談に乗る
- 必要なサービスにつなげる橋渡し役
- 地域や制度の問題解決に取り組む
働く場所
- 市役所の福祉課
- 病院の医療ソーシャルワーカー
- 地域包括支援センター
【関連記事】介護職から社会福祉士へのステップアップ方法を詳しく解説しています。
「介護職から社会福祉士への「キャリアチェンジ」成功の3ステップ
ステップ2:介護福祉士(ケアワーカー)
何をする人?
- 高齢者や障害者の日常生活をサポート
- 食事、入浴、排泄などの身体介護
- 利用者さんの心のケアも大切な仕事
働く場所
- 特別養護老人ホーム
- デイサービス
- 訪問介護事業所
「介護福祉士の資格取得方法について、中卒からでも目指せる3つのルートと実務経験を効率的に積む方法については、
【中卒からでも大丈夫】介護福祉士の受験資格を取得する3つのルート]で詳しく解説しています。」
ステップ3:保育士
何をする人?
- 0歳〜小学校就学前の子どもの保育
- 子どもの成長発達を支援
- 保護者への子育て支援
働く場所
- 保育園、認定こども園
- 児童養護施設
- 子育て支援センター
ステップ4:精神保健福祉士(PSW)
何をする人?
- 精神的な病気や障害のある人の支援
- 社会復帰や就労支援
- 家族への相談支援
働く場所
- 精神科病院
- 就労継続支援事業所
- 市町村の精神保健センター
💡ワンポイント解説
これら4つの資格は、それぞれ専門分野がありますが、実際の現場では連携して働くことが多いです。例えば、認知症の高齢者の支援では、介護福祉士が日常ケアを行い、社会福祉士が家族の相談に乗り、精神保健福祉士が心理的ケアを担当するといった具合です。
福祉の仕事が支える社会保障制度について詳しくはこちら:
→ 【中学生でもわかる】社会保障制度って何?身近な例で簡単解説
3. 【体験談】実際に働いてみた/関わった経験
🌟実際の感じたこと
認知症高齢者との関わり(高齢者施設)
教科書では「受容的態度で接する」と学びましたが、現実は全然違いました。同じことを10回聞かれても笑顔で答える日もあれば、正直「また?」と思ってしまう日も。認知症の方が突然怒り出したり、帰宅願望で施設から出ようとしたり。理性を保つのが精一杯の時もありました。
不登校で精神疾患のある児童との関わり(児童福祉施設)
中学生の男の子で不登校、うつ病の診断もありました。「学校に行こう」と励ましても逆効果。教科書通りの支援では全く響かない。その子のペースに合わせて、まずは一緒にゲームをしたり、好きなアニメの話をしたりすることから始めました。関係作りに半年以上かかりました。
てんかん発作が頻繁に起こる知的障害者の支援(障害者施設)
重度の知的障害とてんかんを併せ持つ利用者さん。一日に何度も発作が起こり、その度に救急対応。医師の指示通りに薬を管理し、発作時の対応マニュアルもありましたが、実際の現場では一人ひとりの発作の特徴が違うため、その人に合わせた対応を覚える必要がありました。
🌟支援者としての視点
現場でよく見る現実
- 人手不足で一人ひとりにじっくり向き合う時間が取れない
- 診療報酬や給付費のために、本当に必要な支援よりも「算定できる支援」が優先される場面がある
- 同じ病名・障害名でも、全く違う支援が必要な人ばかり
スタッフが躓きやすいポイント
- 理想と現実のギャップに打ちのめされる
- 利用者さんからの暴言や暴力に対処できない
- 家族や他職種との関係がうまくいかない
乗り越えるためのコツ
- 完璧を求めすぎない。「今日はこれができた」という小さな成功を大切にする
- 一人で抱え込まず、チームで支援することを心がける
- 利用者さん一人ひとりが違うということを受け入れる
【関連記事】私が福祉職を選んだ本当の理由をお話しします。
福祉の仕事に就職した動機は「絶望的にコミュ障だった私が人生を変えた話」
4. 【注意点・デメリット】知っておくべきこと
仕事の厳しい現実
- 給料が安い:他の職種と比べて給与水準が低い傾向
- 体力的にきつい:夜勤、力仕事、精神的ストレスが多い
- 感情労働:常に笑顔で、自分の感情をコントロールする必要がある
- 責任が重い:人の命や人生に関わる重大な責任を負う
【関連記事】福祉職の具体的な年収について詳しく解説しています。
【福祉職の給料事情】4つの資格の年収を比較
よくある勘違い
- 「優しい人なら誰でもできる」→ 専門知識と技術が必要
- 「やりがいがあれば給料は気にしない」→ 生活できる給料も大切
- 「利用者さんはみんな感謝してくれる」→ 理不尽な扱いを受けることもある
向いていない人の特徴
- 完璧主義すぎる人
- 他人の気持ちに共感しすぎて疲れてしまう人
- 変化に対応するのが苦手な人
- 自分の価値観を押し付けがちな人
5. 【まとめ】それでも福祉の仕事を選ぶ理由
1. 一人ひとりが違うから、毎日が学びになる
教科書通りにいかないからこそ、創意工夫が求められ、成長できます。
2. 小さな変化に大きな喜びを感じられる
利用者さんの笑顔、できなかったことができるようになった瞬間、「ありがとう」の一言。これらが何よりの報酬です。
3. 社会にとって本当に必要な仕事
高齢化社会、格差社会の中で、福祉の仕事の重要性はますます高まっています。
【関連記事】
福祉の現場で支援している立場として、実際に制度を利用した体験談もお伝えしています:
→ 【実体験】発達障害で障害者手帳を取得した理由とメリット5つ
関連情報・次のアクション
🔗関連記事(公開予定)
- 【社会福祉士になるには】受験資格から合格のコツまで完全ガイド
- 【福祉職の給料事情】4つの国家資格の年収を現役職員が比較
読者との交流
💬最後に
この記事が「福祉の仕事について知りたい」という方の参考になれば嬉しいです。
福祉の仕事は確かに大変です。理想と現実のギャップに悩むこともあります。でも、だからこそ得られる達成感や成長もあります。
あなたの体験も教えてください!
- 福祉の仕事を目指している方の不安や疑問
- 現在福祉職として働いている方の体験談
- 「この資格について詳しく知りたい」というリクエスト
コメントやメッセージでお聞かせください😊
一緒に「福祉の仕事の本当のところ」を共有していきましょう!