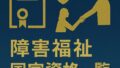こんなお悩みありませんか?
- 公的年金制度って何だかよく分からない
- 年金について調べたいけど、専門用語が多すぎて理解できない
- 将来年金がもらえるか不安だけど、どう準備したらいいの?
この記事で分かること
✅ 公的年金制度の基本的な仕組み
✅ 国民年金・厚生年金の違いと手続き方法
✅ 福祉専門職として関わった実体験・当事者目線での気づき
この記事を書いている人

福祉の専門職(社会福祉士・精神保健福祉士)で、
発達障害の当事者でもある私が、業務経験と自身の手続き体験の両方から、
専門知識と実体験を交えて分かりやすく解説します。
「初めてこのブログをお読みの方は、
**[【はじめまして】福祉のプロ×当事者が始める理由]**
で運営者の詳しいプロフィールと、なぜこのブログを始めたのかをご紹介しています。」
📂 カテゴリー別記事一覧
🏛️ 社会保障制度 | 💼 福祉のお仕事 | 🧠 障害と生きづらさ
※本記事は社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・保育士の資格を持つ私の実体験や専門知識、福祉制度の理解に基づく情報提供です。医学的診断や治療の代替となるものではありません。
1. 【基本編】公的年金制度とは?中学生でも分かる基礎知識
公的年金制度を簡単に
「みんなでお金を出し合って、老後や困った時に支えあう仕組み」です
公的年金制度は、国が運営する社会保険制度の一つです。現在働いている人たちが保険料を支払い、そのお金で今の高齢者や障害を持つ方々を支える「世代間扶養」という考え方がベースになっています。
なぜこの制度があるの?
🎯 主な目的
- 老後の生活を支える(老齢年金)
- 病気やけがで働けなくなった時の生活保障(障害年金)
- 家族の大黒柱が亡くなった時の遺族の生活保障(遺族年金)
誰が利用できるの?
基本的に日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入対象です。
📊 加入者の種類
| 種類 | 対象者 | 具体例 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業・学生・無職の方 | フリーランス、大学生、専業主婦(夫) |
| 第2号被保険者 | 会社員・公務員 | サラリーマン、教師、看護師 |
| 第3号被保険者 | 第2号被保険者の扶養配偶者 | 年収130万円未満の専業主婦(夫) |
2. 【詳細編】公的年金制度の具体的な内容・手順
年金制度は「2階建て構造」になっています
┌─────────────────────┐
│ 厚生年金保険(2階部分) │ ← 会社員・公務員が加入
├─────────────────────┤
│ 国民年金(1階部分) │ ← 全員が加入する基礎部分
└─────────────────────┘
ステップ1:国民年金への加入手続き
🏃♀️ いつ手続きが必要?
- 20歳になった時
- 就職・退職した時
- 結婚・離婚した時
- 住所が変わった時
📝 手続きする場所
- 市区町村の国民年金窓口
- 年金事務所
- 会社(厚生年金の場合)
ステップ2:保険料の支払い
💰 保険料(2024年度)
- 国民年金:月額16,980円
- 厚生年金:給与に応じて決定(会社と折半)
ステップ3:年金の受給
📅 受給開始年齢(老齢年金)
- 原則65歳から
- 早めに受け取る場合:60歳~(減額あり)
- 遅めに受け取る場合:66歳~75歳(増額あり)
💡ワンポイント解説
当事者として気づいた重要なポイント:
発達障害などで一般就労が困難な場合、障害年金の受給可能性があります。
20歳前から障害がある場合の「20歳前障害による障害基礎年金」など、特別な制度もあるので、諦めずに相談することが大切です。
🌟 障害年金についてもっと知りたい方へ
発達障害をお持ちの方は、条件を満たせば障害年金を受給できる可能性があります。
追納制度について知っておこう!
学生時代や無職の頃に免除や猶予を受けていた期間の保険料は、10年以内であれば後から支払うことができます。
これを「追納」といいます。追納すると将来の年金額が増えるので、経済的に余裕ができたら検討する価値があります。
年金制度の基本となる社会保障制度の4つの柱について詳しく知りたい方は、
**【中学生でもわかる】社会保障制度って何?身近な例で簡単解説**をご参照ください。」
3. 【体験談】実際に使ってみた/関わった経験
🌟当事者としての体験
年金手帳を失くして大慌び!
発達障害の特性で物の管理が苦手な私は「年金手帳がない!」と大慌てしては再発行を繰り返すうちに、複数の年金手帳が手元に集まりました。
※令和4年からは年金手帳は基礎年金番号に切り替わりました。
ちなみに運転免許証は3回紛失しました😢
運転免許証の番号の一番最後は再発行した数字になります。2桁になったらどうなるんでしょうか?
ねんきん定期便で将来設計
毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」を見て、将来もらえる年金額をチェックしています。
最初は見方が分からなかったのですが、年金事務所で説明してもらい、今では家計の参考にしています。
年金制度以外にも、社会保障制度全体について理解を深めたい方は、社会保障制度の歴史をわかりやすく解説の記事もおすすめです。
🌟支援者としての視点
現場でよく見る事例
- 学生時代の未納が発覚するケース
- 手続きを忘れていた
- 経済的に支払いが困難だった → 学生納付特例制度を活用すれば解決できます
- 転職時の切り替え漏れ
- 退職後の国民年金加入手続きを忘れる → 14日以内に手続きが必要です
- 追納を検討するタイミング
- 就職して収入が安定した時
- 昇進・昇給で余裕ができた時 → 10年以内なら追納可能、早めがお得です
スムーズに進めるコツ
- 必要書類を事前に確認する
- 分からないことは遠慮せず質問する
- 定期的に加入記録をチェックする
4. 【注意点・デメリット】知っておくべきこと
⚠️ 利用時の注意点
保険料の未納は将来に大きく影響します
- 未納期間があると受給額が減る
- 25年間の加入期間がないと受給できない(2017年から10年に短縮)
よくある勘違い
❌ 「年金制度は破綻するから払わない方がいい」
→ 制度は持続可能性を保つため定期的に見直されています
❌ 「厚生年金に入れば国民年金は払わなくていい」
→ 厚生年金に加入すると自動的に国民年金にも加入になります
デメリット・制限事項
- インフレリスクがある
- 支給開始年齢の引き上げ可能性
- 現役世代の負担増加傾向
5. 【まとめ】今日から使える3つのポイント
1. まずは「ねんきんネット」に登録しよう
インターネットで24時間いつでも年金記録を確認できます
2. 保険料が払えない時は「免除制度」を活用、後から「追納」も検討
- 未納にせず、必ず減免手続きを行いましょう
- 免除・猶予を受けた期間は10年以内なら追納可能
- 追納すると将来の年金額が増えます
3. 分からないことは年金事務所に相談
電話でも窓口でも、専門職員が丁寧に説明してくれます
💬最後に
この記事が「公的年金制度について知りたい」という方の参考になれば嬉しいです。
年金制度は複雑に見えますが、基本を理解すれば安心して将来に備えることができます。私自身も最初は難しく感じましたが、一つずつ理解していくことで、今では年金を含めた人生設計ができるようになりました。
あなたの体験も教えてください!
- 年金制度で困った経験がある方
- 「この部分をもっと詳しく知りたい」というリクエスト
- 実際に手続きをした体験談
コメントやメッセージでお聞かせください😊
一緒に「将来への安心」を見つけていきましょう!
参考文献・リンク
- 日本年金機構公式サイト
- 厚生労働省「公的年金制度の概要」
- ねんきんネット