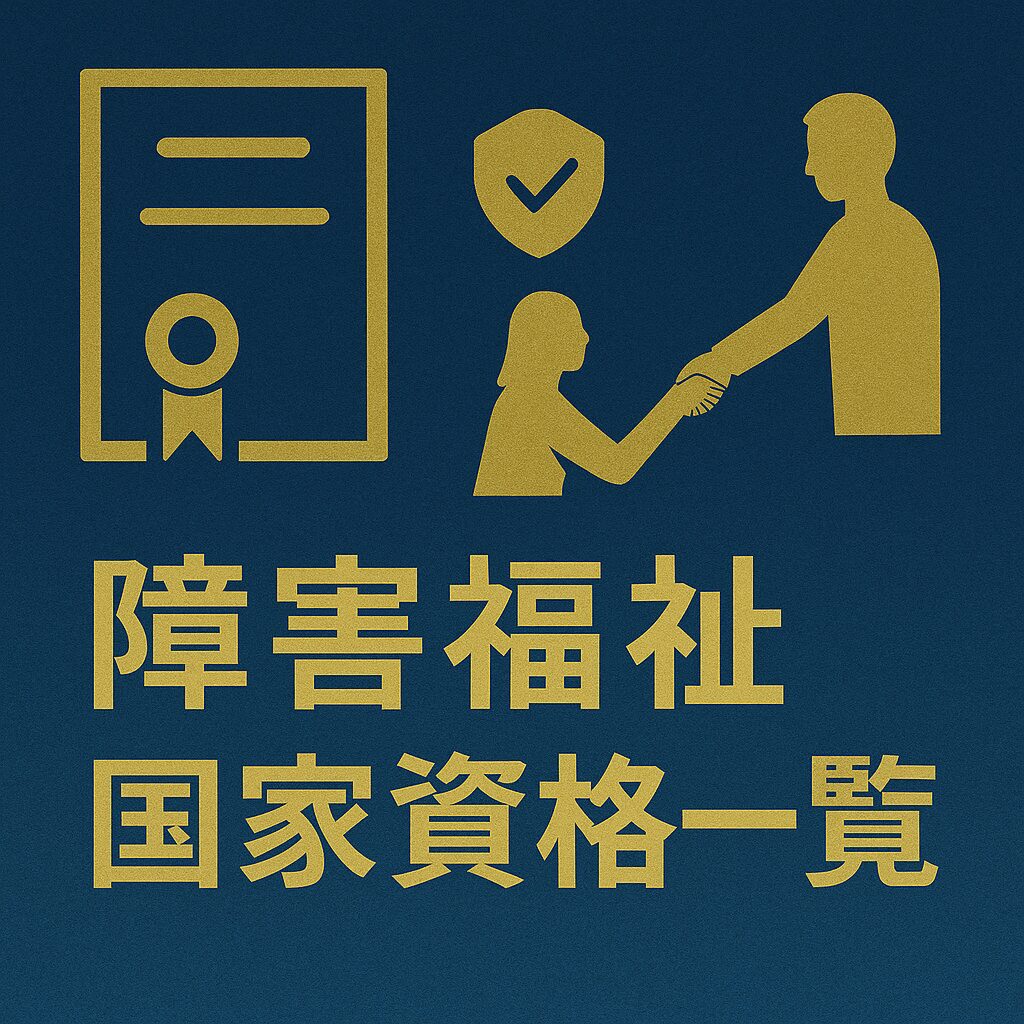こんなお悩みありませんか?
- 障害福祉の仕事に興味があるけど、どんな国家資格があるか分からない
- 国家資格を取って障害福祉の専門職として働きたいけど、種類が多すぎて迷っている
- それぞれの資格の違いや、どの資格が自分に向いているか知りたい
- 国家資格を取るメリットや具体的な取得方法が知りたい
この記事で分かること
✅ 障害福祉で活かせる国家資格の種類と特徴
✅ 各資格の具体的な業務内容と活躍の場
✅ 資格取得の方法、期間、費用の目安
✅ 実際の現場で「本当に求められる」国家資格はどれか
この記事を書いている人

福祉の専門職(社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・保育士)で、
発達障害の当事者でもあるバッキーが、現場での実体験と専門知識の両方から解説します。
国家資格取得の実体験と、様々な専門職と連携してきた現場経験をもとに、リアルな情報をお届けします。
「初めてこのブログをお読みの方は、
**[【はじめまして】福祉のプロ×当事者が始める理由]**
で運営者の詳しいプロフィールと、なぜこのブログを始めたのかをご紹介しています。」
📂 カテゴリー別記事一覧
🏛️ 社会保障制度 | 💼 福祉のお仕事 | 🧠 障害と生きづらさ
※本記事は社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・保育士の資格を持つ私の実体験や専門知識、福祉制度の理解に基づく情報提供です。医学的診断や治療の代替となるものではありません。
1. 【基本編】障害福祉を支える国家資格とは?
簡単に言うと、障害福祉の国家資格は「国が認めた専門性の証明書」です
障害のある方の生活を支援するために、国が定めた厳格な基準をクリアした専門職の証明が国家資格です。民間資格と違って:
- 社会的信頼度が圧倒的に高い
- 就職・転職で有利になる
- 給料や待遇が良くなる
- 専門性を活かした独立開業も可能(一部の資格)
といったメリットがあります。
障害福祉で活躍する国家資格の全体図
【障害福祉を支える国家資格】
🏥 医療・リハビリ系
├─ 理学療法士 ──── 身体機能の回復支援
├─ 作業療法士 ──── 日常生活動作の支援
├─ 言語聴覚士 ──── コミュニケーション支援
└─ 看護師 ────── 医療的ケア全般
🧠 心理・相談支援系
├─ 公認心理師 ──── 心理的支援の専門家
├─ 社会福祉士 ──── 相談支援のスペシャリスト
└─ 精神保健福祉士 ── 精神障害特化の相談支援
🤝 生活支援系
├─ 介護福祉士 ──── 日常生活支援のプロ
└─ 保育士 ────── 児童の発達支援
※視能訓練士も国家資格ですが、視機能特化のため除外
どの資格が最も重要?
答え:支援したい分野によって異なります
| あなたの志向 | おすすめ国家資格 | 理由 |
|---|---|---|
| 相談支援がメイン | 社会福祉士、精神保健福祉士 | 計画作成や制度活用の専門性 |
| 直接的な生活支援 | 介護福祉士、作業療法士 | 身体的・生活的支援技術 |
| 心の支援を重視 | 公認心理師、精神保健福祉士 | カウンセリングや心理療法 |
| 身体機能の回復 | 理学療法士、作業療法士 | 専門的なリハビリ技術 |
| 医療的なケア | 看護師、言語聴覚士 | 医療知識と技術 |
2. 【詳細編】各国家資格の完全解説
🏥 医療・リハビリ系国家資格
理学療法士(PT)
こんな人におすすめ: 身体機能の回復を通じて、障害者の自立を支援したい
【理学療法士の取得ルート】
高校卒業
↓
理学療法士養成校(3-4年)
↓
国家試験受験
↓
理学療法士免許取得
- 業務内容: 身体機能評価、運動療法、物理療法、歩行訓練
- 活躍の場: 病院、リハビリ施設、障害者支援施設、訪問リハビリ
- 費用目安: 養成校学費 約300-600万円、受験料 10,100円
- 合格率: 約85%
- 平均年収: 約350-450万円
作業療法士(OT)
こんな人におすすめ: 日常生活動作を通じて、その人らしい生活を支援したい
- 業務内容: 日常生活動作訓練、認知機能訓練、福祉用具の選定・指導
- 活躍の場: 病院、デイサービス、就労支援事業所、特別支援学校
- 費用目安: 理学療法士とほぼ同じ
- 合格率: 約80%
- 平均年収: 約340-440万円
言語聴覚士(ST)
こんな人におすすめ: コミュニケーション障害のある方の支援に特化したい
- 業務内容: 言語機能検査・訓練、摂食嚥下機能訓練、聴覚検査
- 活躍の場: 病院、リハビリ施設、特別支援学校、児童発達支援センター
- 費用目安: 養成校学費 約300-600万円、受験料 34,000円
- 合格率: 約65%
- 平均年収: 約350-450万円
看護師
こんな人におすすめ: 医療的ケアを通じて障害者の健康を支えたい
- 業務内容: 健康管理、医療的ケア、服薬管理、家族への健康指導
- 活躍の場: 病院、訪問看護、障害者支援施設、重症心身障害者施設
- 費用目安: 養成校学費 約150-500万円、受験料 5,400円
- 合格率: 約90%
- 平均年収: 約400-550万円
💡ワンポイント解説(現場からの実感)
医療・リハビリ系資格の強み:
✨ 専門技術が明確 → 他職種にできない専門性がある
✨ 就職先が豊富 → 病院から福祉施設まで幅広い選択肢
✨ チーム医療の要 → 多職種連携の中核として活躍
✨ 独立開業も可能 → 訪問リハビリなどで起業する人も
🧠 心理・相談支援系国家資格
公認心理師
こんな人におすすめ: 心理学の専門知識で障害者の心の支援をしたい
【公認心理師の取得ルート】
ルート1: 4年制大学(指定科目)→ 大学院(指定科目)→ 国家試験
ルート2: 4年制大学(指定科目)→ 認定施設で実務経験2年 → 国家試験
- 業務内容: 心理査定、心理療法、心理的支援、関係者への助言
- 活躍の場: 病院、障害者支援施設、相談支援事業所、特別支援学校
- 費用目安: 大学院ルート約400-600万円、実務経験ルート約200-300万円
- 合格率: 約65%
- 平均年収: 約350-500万円
社会福祉士
こんな人におすすめ: 制度やサービスを活用して、総合的な相談支援をしたい
- 業務内容: 生活相談、サービス利用計画作成、関係機関との連携、権利擁護
- 活躍の場: 相談支援事業所、障害者支援施設、行政機関、社会福祉協議会
- 取得方法: 福祉系大学4年 または 実務経験+養成施設
- 費用目安: 養成施設約100-150万円、受験料19,370円
- 合格率: 約30%
- 平均年収: 約300-450万円
精神保健福祉士
こんな人におすすめ: 精神障害のある方の地域生活支援に特化したい
- 業務内容: 精神障害者の相談支援、医療機関との連携、就労支援、家族支援
- 活躍の場: 精神科病院、就労支援事業所、相談支援事業所、行政機関
- 取得方法: 社会福祉士とほぼ同じルート
- 費用目安: 養成施設約100-150万円、受験料17,610円
- 合格率: ※約65%
- 平均年収: 約320-450万円
※精神保健福祉士の合格率が高いのは、社会福祉士と共通科目が被っているから先に社会福祉士を取得した人が、専門科目だけで受験できるところにあると思います。
🤝 生活支援系国家資格
介護福祉士
こんな人におすすめ: 日常生活の直接支援を通じて、利用者の生活を支えたい
- 業務内容: 食事・入浴・排泄介助、移動介助、生活支援、家族への指導
- 活躍の場: 障害者支援施設、グループホーム、デイサービス、訪問介護
- 取得方法: 介護福祉士養成校2年 または 実務経験3年+実務者研修
- 費用目安: 養成校約200万円、実務者研修約15万円、受験料18,380円
- 合格率: 約75%
- 平均年収: 約280-380万円
保育士
こんな人におすすめ: 障害のある子どもの発達支援に関わりたい
- 業務内容: 児童の発達支援、保護者支援、個別支援計画の作成
- 活躍の場: 児童発達支援センター、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
- 取得方法: 保育士養成校修了 または 保育士試験合格
- 費用目安: 養成校約200万円、試験受験料12,950円
- 合格率: 約20%
- 平均年収: 約280-400万円
3. 【体験談】実際の資格取得と現場での活用
🌟当事者としての体験
私の国家資格取得歴:
- 福祉系短大卒業後、なんと10年間のブランクを経て社会福祉士に挑戦
- 一発合格! 諦めていた国家資格への道が開けた瞬間でした ✨
- その勢いで同年に通信制大学に編入 → 精神保健福祉士も取得成功!
- 2つの国家資格を手にして、現場での信頼度が格段にアップ
実際に国家資格を取得してみて分かったこと:
- 国家資格の威力は想像以上 → 利用者さんや同僚からの信頼が全然違う
- 転職時の選択肢が劇的に拡大 → 管理職や専門職のポジションに応募しやすい
- 給料・待遇が明らかに改善 → 資格手当だけでなく、基本給も上がるところもある
- 専門性を活かした仕事ができる → 単なる「お世話」ではなく「専門的支援」として認識される
「もっと早く知りたかった!」と思ったポイント:
- 国家資格は年齢に関係なく取得可能 → 30代、40代からでも全然遅くない!
- 実務経験が国家試験に活かせる → 現場を知っているからこそ理解が深い
- 複数の国家資格の組み合わせが強力 → 社会福祉士+精神保健福祉士で専門性倍増
🌟支援者としての視点
現場でよく見る各国家資格の活躍:
理学療法士・作業療法士:
- 身体機能の維持・改善で、利用者の「できること」を増やす
- 福祉用具の選定で、自立度を大幅に向上させる
- 「この動作はPT・OTに相談しよう」と頼りにされる存在
公認心理師・精神保健福祉士:
- 行動面での課題解決で、本人・家族・支援者全体が楽になる
- カウンセリング技術で、利用者の心の安定を図る
- 「心の専門家」として、チーム全体から相談される
社会福祉士:
- 制度知識の豊富さで、利用者に最適なサービスを提案
- 関係機関との調整で、総合的な支援体制を構築
- 「困ったときの相談先」として、現場の要となる
スムーズに資格を活かすコツ:
- 現場経験を積んでから国家資格取得 → 理論と実践が結びつく
- 自分の得意分野を明確にする → 専門性を前面に出して活躍
- 他職種との連携を大切にする → チーム支援の中で真価を発揮
4. 【注意点・デメリット】知っておくべきこと
取得時の注意点
⚠️ 取得にかかる時間と費用が高額
【各資格の取得コスト比較】
高コスト(400万円以上)
├─ 公認心理師(大学院ルート)
├─ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
└─ 看護師(私立大学の場合)
中コスト(150-300万円)
├─ 公認心理師(実務経験ルート)
├─ 社会福祉士・精神保健福祉士(養成施設)
├─ 介護福祉士(養成校)
└─ 保育士(養成校)
低コスト(50万円以下)
├─ 介護福祉士(実務経験ルート)
└─ 保育士(試験受験)
⚠️ 国家試験の合格率にバラつきがある
- 社会福祉士(約30%)、保育士試験(約20%)→ 難易度高
- 言語聴覚士(約65%)、精神保健福祉士(約65%)→ 中程度
- 理学療法士(約85%)、看護師(約90%)→ 比較的易
よくある勘違い
❌ 「国家資格があれば高収入確定」 → ⭕ 職場や地域によって給料に大きな差がある
❌ 「1つの国家資格で全ての支援ができる」→ ⭕ 各資格には専門領域があり、チーム支援が基本
❌ 「難しい資格ほど現場で重宝される」 → ⭕ 現場のニーズと資格の専門性がマッチすることが重要
デメリット・制限事項
📚 継続的な学習が必要
- 制度改正への対応(特に社会福祉士、精神保健福祉士)
- 技術の進歩への追随(特にリハビリ系、看護師)
- 研修参加や学会発表などの自己研鑽
🏥 勤務先による業務内容の違い
- 同じ資格でも、病院と福祉施設では業務内容が大きく異なる
- 法人の方針によって、専門性を活かせる度合いが変わる
- 「思っていた仕事と違う」というミスマッチの可能性
💼 責任の重さ
- 国家資格保持者として、より高い専門性と責任を求められる
- 利用者・家族からの期待値が高い
- 法的な責任を問われる場面もある
5. 【まとめ】今日から使える3つのポイント
1. 自分の志向に合った国家資格を選ぼう
「人気だから」「給料が高いから」ではなく、「何をして社会貢献したいか」で選ぶのが成功の秘訣です。
2. 現場経験を積んでから国家資格取得を検討
まずは現場で働いて、どの専門職が必要か・どの業務に興味があるかを実感してから決めるのが効率的です。
3. 長期計画を立てて段階的に取得
いきなり難易度の高い資格を目指さず、働きながら無理なく取得できる計画を立てましょう。
読者との交流
💬最後に
この記事が「障害福祉の国家資格について知りたい」という方の参考になれば嬉しいです。
国家資格の取得は確かに大変ですが、障害のある方の「その人らしい生活」を専門的に支援できる、とてもやりがいのある道です。あなたの人生経験や興味のある分野を活かして、ぜひ挑戦してみてください 😊
あなたの体験も教えてください!
- 実際に国家資格を取得された方の体験談
- 「どの資格にするか悩んでいる」というお悩み
- 「この資格の現場での実際を知りたい」というリクエスト
コメントやメッセージでお聞かせください😊 一緒に「生きやすさ」を見つけていきましょう!
参考文献
- 厚生労働省「各種国家試験情報」
- 社会福祉振興・試験センター「資格取得の手引き」
- 各職能団体公式サイト「資格取得ガイド」
- 全国社会福祉士会「ソーシャルワーカーデー」
。