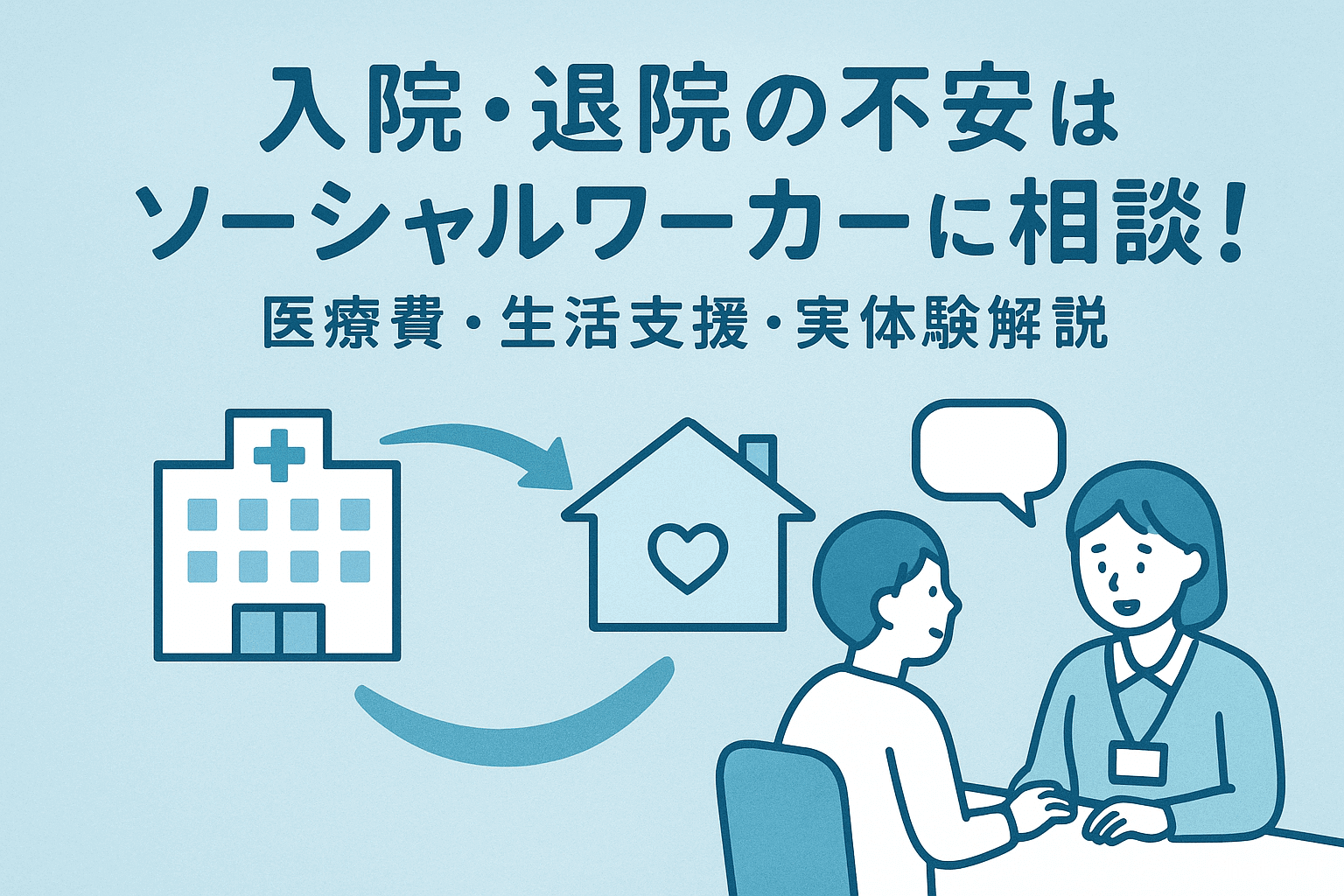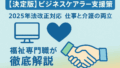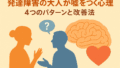こんなお悩みありませんか?
- 入院中の医療費の支払いで困っている
- 退院後の生活について不安があるけど、どこに相談したらいいか分からない
- ソーシャルワーカーがいるって聞いたけど、何をしてくれる人なの?
この記事で分かること
✅ 医療ソーシャルワーカーの役割と業務内容
✅ 入院中に相談できる具体的な内容と手順
✅ 実際に活用してみた体験談・注意点
この記事を読めば、入院中の不安を一人で抱え込まず、専門職のサポートを受けながら安心して治療に専念し、退院後の生活設計まで見通しを立てられるようになります。
「初めてこのブログをお読みの方は、
**[【はじめまして】福祉のプロ×当事者が始める理由]**
で運営者の詳しいプロフィールと、なぜこのブログを始めたのかをご紹介しています。」
この記事を書いている人

福祉の専門職(社会福祉士・精神保健福祉士)としてソーシャルワークに携わり、発達障害の当事者でもあるバッキーが、専門知識と実体験の両方から入院中の不安を解消するソーシャルワーカーの活用術を詳しく解説します。
📂 カテゴリー別記事一覧
🏛️ 社会保障制度 | 💼 福祉のお仕事 | 🧠 障害と生きづらさ
本記事は社会福祉士・精神保健福祉士の資格を持つ私の専門知識と個人の体験談に基づく情報提供です。医学的診断や治療の代替となるものではありません
1. 【基本】医療ソーシャルワーカー(MSW)とは?入院中の役割を解説
簡単に言うと、医療ソーシャルワーカーは「入院中の生活の困りごとを一緒に解決してくれる専門職」です
医療ソーシャルワーカー(MSW)は、病院で働く社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持った専門職です。患者さんやご家族が抱える経済的な問題、社会復帰への不安、家族関係の悩みなど、医療以外の様々な困りごとをサポートします。
医療ソーシャルワーカー(MSW)の3つの基本機能
1️⃣ 直接援助技術(ケースワーク)
- 患者さん一人ひとりと向き合い、個別の課題解決をサポート
- 面接・相談を通じて、本人の強み(ストレングス):本人が持っている、困難を乗り越えるための力や資源を見つける
- 自己決定を尊重し、本人が納得できる選択肢を一緒に考える
2️⃣ 間接援助技術(コーディネーション)
- 医師・看護師・理学療法士など多職種チームの連携を促進
- 院内外の社会資源(制度・サービス・施設)をつなぐ
- 退院支援カンファレンスの企画・運営
3️⃣ 社会への働きかけ(ソーシャルアクション)
- 制度の狭間で困っている患者さんの声を政策提言に反映
- 地域連携ネットワークづくりに参画
- 社会制度の改善に向けた活動
病院におけるMSWの専門的な視点
医療チームでの独自の視点:
| 職種 | 専門的な視点 | 主な役割 |
|---|---|---|
| 医師 | 病気を治す(医学的視点) | 診断・治療 |
| 看護師 | 日常生活を支える(看護学的視点) | 療養上のケア |
| ソーシャルワーカー | 生活全体を見る(社会福祉学的視点) | 生活課題の解決支援 |
ソーシャルワーカーは多くの場合、病院の地域連携室または相談室に在籍しています。
具体的な専門性:
- 👤 その人らしさを大切にした支援
- 🌍 環境との相互作用を重視した課題分析
- 🤝 エンパワメント(本人の力を引き出す):本人が持っている力や可能性を信じて、それを発揮できるよう支援すること
- 📊 社会正義の実現に向けた取り組み
なぜこの職種があるの?
病気になると、治療だけでなく様々な問題が生じます:
- 💰 経済面:医療費や生活費の心配
- 🏠 住環境:退院後の住まいや介護環境
- 👨👩👧👦 家族関係:病気による家族への影響
- 💼 社会復帰:仕事や学校への復帰の不安
これらの問題を解決しないと、治療に専念できなかったり、退院後の生活が困難になることがあります。そこで**「人と環境の相互作用」を専門とする**ソーシャルワーカーが医療チームの一員として配置されています。
ソーシャルワーカーの専門教育について
大学で学ぶ専門分野:
- ソーシャルワークの基盤と専門職:ソーシャルワークの定義・価値・倫理
- ソーシャルワークの理論と方法:援助技術・面接技法・支援プロセス
- 地域福祉と包括的支援体制:地域共生社会・多職種連携・地域ネットワーク【新設科目】
- 医学概論:疾病・障害への理解
- 社会保障:制度・政策の知識
- 心理学と心理的支援:人間行動の理解・心理的支援技法
- 社会学と社会システム:社会構造・社会問題の分析
- 刑事司法と福祉:触法者支援・社会復帰支援【新設科目】
実習経験:
- ソーシャルワーク実習(240時間以上・2ヵ所以上)で実践力を習得【180時間から増加】
- ソーシャルワーク実習指導による専門指導を実施
誰が利用できるの?
- 🏥 入院患者さん(年齢・疾患問わず)
- 👨👩👧👦 患者さんのご家族
- 🚑 外来患者さん(病院によって異なる)
- 🏠 退院後の継続相談(地域連携室経由で一定期間対応可能な場合あり)
利用料は基本的に無料です。相談したからといって追加の費用がかかることはありません。
2. 【具体例】入院中 ソーシャルワーカーに相談できる医療費・退院の不安
相談できる内容一覧表
| カテゴリー | 具体的な相談内容 | 利用できる制度・サービス例 |
|---|---|---|
| 💰 医療費・経済面 | 医療費の支払い不安、生活費の心配 | 高額療養費制度、医療費助成、生活保護 |
| 🏠 退院後の生活環境 | 住環境整備、介護サービス | 介護保険、訪問看護、施設入所 |
| 👨👩👧👦 家族・人間関係 | 家族間の調整、面会問題 | 家族会議サポート、関係調整 |
| 💼 社会復帰・就労 | 職場復帰、障害への対応 | 障害者手帳、就労移行支援、障害年金 |
🏥 医療費・経済面の相談
- 高額療養費制度の申請手続き
- 医療費助成制度の紹介
- 生活保護や各種手当の相談
- 支払い方法の相談(分割払い等)
🏠 退院後の生活環境整備
- 介護保険サービスの申請・調整
- 訪問看護や訪問介護の手配
- 施設入所の相談・見学調整
- 住宅改修の相談
- 退院支援計画の作成・調整
👨👩👧👦 家族・人間関係の調整
- 家族間の話し合いのサポート
- キーパーソン(連絡窓口)の調整
- 病状説明時の立ち会い
- 面会に関する調整
💼 社会復帰・就労支援
- 障害者手帳の申請サポート
- 就労移行支援の紹介
- 職場復帰に向けた調整
- 障害年金の相談
【関連記事】障害者手帳を取得した体験談はこちらで詳しく書いています:
→ 【実体験】発達障害で障害者手帳を取得した理由とメリット5つ
📋 相談の手順
【ステップ1】 看護師や主治医に「ソーシャルワーカーと話したい」と伝える
【ステップ2】 医療ソーシャルワーカーとの面談日程を調整
【ステップ3】 相談内容を整理して面談に臨む
「遠慮は不要です!」相談のハードルを下げるために
ソーシャルワーカーの仕事は、患者さんの生活を支えること。医療費や退院後の不安は、決して恥ずかしいことではありません。むしろ早期相談で余裕を持った退院準備が可能です。
- 💰 「お金の話は恥ずかしい」 → 経済的な相談は日常業務。プライバシーは厳守されます
- 🤝 「まだ早すぎるかも」 → 入院初期からの相談で、より良い退院支援計画が立てられます
- 👨👩👧👦 「家族だけで決められる」 → 専門職の視点で、見落としがちな制度・サービスをご提案できます
専門家が解説!相談をよりスムーズにするためのコツ
相談前に「何に困っているか」「退院後どんな生活をしたいか」をメモしておくと、より具体的なサポートを受けられます。また、家族の連絡先や収入状況なども整理しておくとスムーズです。
ソーシャルワーカーが面接で重視すること:
- 🎯 本人の意向:「どうしたいか」を最優先で聞き取り
- 💪 ストレングス:これまでどんな困難を乗り越えてきたか
- 🌐 社会資源:活用できる制度・サービス・人的支援の確認
- 📈 将来展望:退院後の生活イメージと段階的目標設定
【関連記事】精神障害に特化した精神保健福祉士について詳しく記事にしています⇩
精神保健福祉士って何する人?🌟仕事内容を本音で解説
3. 【実体験】ソーシャルワーカーを活用してわかったメリットと注意点
当事者として利用して「良かったこと」「困ったこと」
私自身、家族の入院中にソーシャルワーカーさんにお世話になりました。
良かったこと:
- 医療費の支払いについて、高額療養費制度を教えてもらい、月々の負担が大幅に軽減された
- 退院後の訪問介護サービスを事前に手配してもらえたので、スムーズに在宅生活に移行できた
- 家族間で意見が分かれていた治療方針について、第三者として客観的にアドバイスをもらえた
困ったこと・注意点:
- 最初は「お金のことを相談するのが恥ずかしい」と思っていたが、実際は親身に対応してくれた
- 土日祝日は対応していない場合が多いので、平日に相談する必要があった
「もっと早く知りたかった!」と思ったポイント:
入院初期から相談しておけば、退院間際にバタバタせずに済んだということです。
支援者として見た「スムーズなケース」と「躓くポイント」
現場でよく見る事例として以下があります:
スムーズに進むケース:
- 患者さん・家族が積極的に情報提供してくれる
- 早期から相談を開始している
- 家族間で意見がまとまっている
よく躓くポイント:
- 「お金のことを言うのが恥ずかしい」と相談を遅らせる
- 家族間で意見が分かれて調整に時間がかかる
- 退院直前になってから相談を始める
スムーズに進めるコツ:
- 💰 経済状況を正直に伝える(秘密は守られます)
- 📞 家族会議を開いて意見をまとめておく
- ⏰ 入院早期から相談を始める
福祉の専門職として大切にしていること
ソーシャルワーカーの価値観・倫理:
1️⃣ 自己決定の尊重
- 「こうした方がいい」と決めつけるのではなく、本人の意思を最優先
- 複数の選択肢を提示し、本人が選ぶことをサポート
- たとえ専門職から見て「良くない選択」でも、本人の決定を尊重
実例: 在宅復帰を希望する患者さんに、家族は施設入所を勧める場合
→ 双方の気持ちを聞き取り、在宅生活の可能性を具体的に検討してから判断してもらう
2️⃣ 秘密保持の徹底
- 個人情報は本人の同意なしに他者に伝えない
- 守秘義務は法的にも倫理的にも厳格に守る
- 家族間でも、本人の許可なく情報共有はしない
3️⃣ 差別・偏見の排除
- 年齢・性別・疾患・経済状況による区別は一切しない
- 社会的弱者の立場に立った支援を心がける
- 多様性を認め、その人らしい生き方を応援
4️⃣ エンパワメントの視点
- 「何をしてあげるか」ではなく、「本人の力をどう引き出すか」
- 課題だけでなく、強み・資源に着目した支援
- 依存関係ではなく、協働関係を築く
実例: 経済的に困窮している患者さんへの対応
→ 「かわいそう」と同情するのではなく、「今まで頑張ってきた力」を認め、一緒に解決策を考える
他職種との連携で心がけていること
多職種カンファレンスでのソーシャルワーカーの役割:
| 多職種連携の場面 | ソーシャルワーカーの役割 |
|---|---|
| 👥 患者・家族の意向 | 代弁・橋渡し |
| 🌍 生活環境の情報 | 共有・分析 |
| 🤝 退院後の支援体制 | 調整・構築 |
| ⚖️ 倫理的な課題 | 問題提起・検討 |
各職種との連携ポイント:
- 医師:治療方針と生活設計の両立を相談
- 看護師:日常生活の状況と退院後の環境を共有
- 理学療法士:ADL(日常生活動作:食事、排泄、入浴など)向上と住環境整備を連動
- 栄養士:食事制限と家庭環境の調整を協議
- 地域連携担当者:退院支援計画の作成・調整を協働
4. 【重要】入院中 ソーシャルワーカーの限界と利用時の注意点
利用時の注意点
- 相談は平日のみ(土日祝日は基本的に対応なし)
- 時間に限りがある(1回の相談は30分〜1時間程度)
- 病院によって配置人数が異なるため、予約が取りにくい場合がある
よくある勘違い
- ❌「お金を貸してくれる」
→ ⭕制度の紹介や申請のサポート - ❌「何でも解決してくれる」
→ ⭕一緒に解決策を考える - ❌「相談料がかかる」
→ ⭕基本的に無料 - ❌「問題がある人が相談するもの」
→ ⭕予防的な相談も重要 - ❌「家族が代わりに相談すればよい」
→ ⭕本人主体の支援が基本
ソーシャルワーカーの専門性の限界
できること・得意なこと:
| ✅ 対応可能 | 具体例 |
|---|---|
| 社会制度の説明・申請サポート | 高額療養費、介護保険、障害年金など |
| 多職種連携のコーディネート | カンファレンス運営、情報共有 |
| 心理社会的な問題の解決支援 | 家族関係調整、社会復帰支援 |
| 家族調整・関係性の改善 | 話し合いの仲介、合意形成 |
できないこと・専門外のこと:
| ❌ 対応不可 | 理由・代替案 |
|---|---|
| 医学的診断や治療方針の決定 | 医師・看護師が専門 |
| 法律相談 | 弁護士への紹介は可能 |
| 経済的援助(金銭貸与) | 制度紹介・申請支援のみ |
| 強制的な問題解決 | 本人の意思に反する支援は不可 |
他職種への紹介が必要な場合:
- 🏥 医療的課題→ 医師・看護師
- ⚖️ 法的問題→ 弁護士・司法書士
- 💰 債務整理→ ファイナンシャルプランナー
- 🧠 精神的ケア→ 臨床心理士・精神保健福祉士
【関連記事】精神障害に特化した精神保健福祉士について詳しく記事にしています⇩
精神保健福祉士って何する人?🌟仕事内容を本音で解説
デメリット・制限事項
- 即座に問題解決できるわけではない(手続きに時間がかかる制度もある)
- 病院外の問題には限界がある
- 法的な相談は専門外(弁護士への紹介は可能)
5. 【まとめ】入院中 ソーシャルワーカーを最大限活用するための3つのコツ
- 💡早期相談:入院初期から積極的に相談して、退院準備を余裕を持って進める
- 📝情報整理:経済状況や家族構成、退院後の希望を事前にまとめて効率的な相談にする
- 🤝チーム連携:医師・看護師・ソーシャルワーカーと連携して、治療と生活の両面からサポートを受ける
💬最後に
この記事が「入院中の不安を解消したい」「ソーシャルワーカーについて知りたい」という方の参考になれば嬉しいです。
あなたの体験も教えてください!
- 実際にソーシャルワーカーを利用された方の体験談
- 「こんなことで困っている」というお悩み
- 「この部分をもっと詳しく知りたい」というリクエスト
コメントやメッセージでお聞かせください😊 一緒に「生きやすさ」を見つけていきましょう!
この記事が役に立ったら、ぜひSNSでシェアしてください!