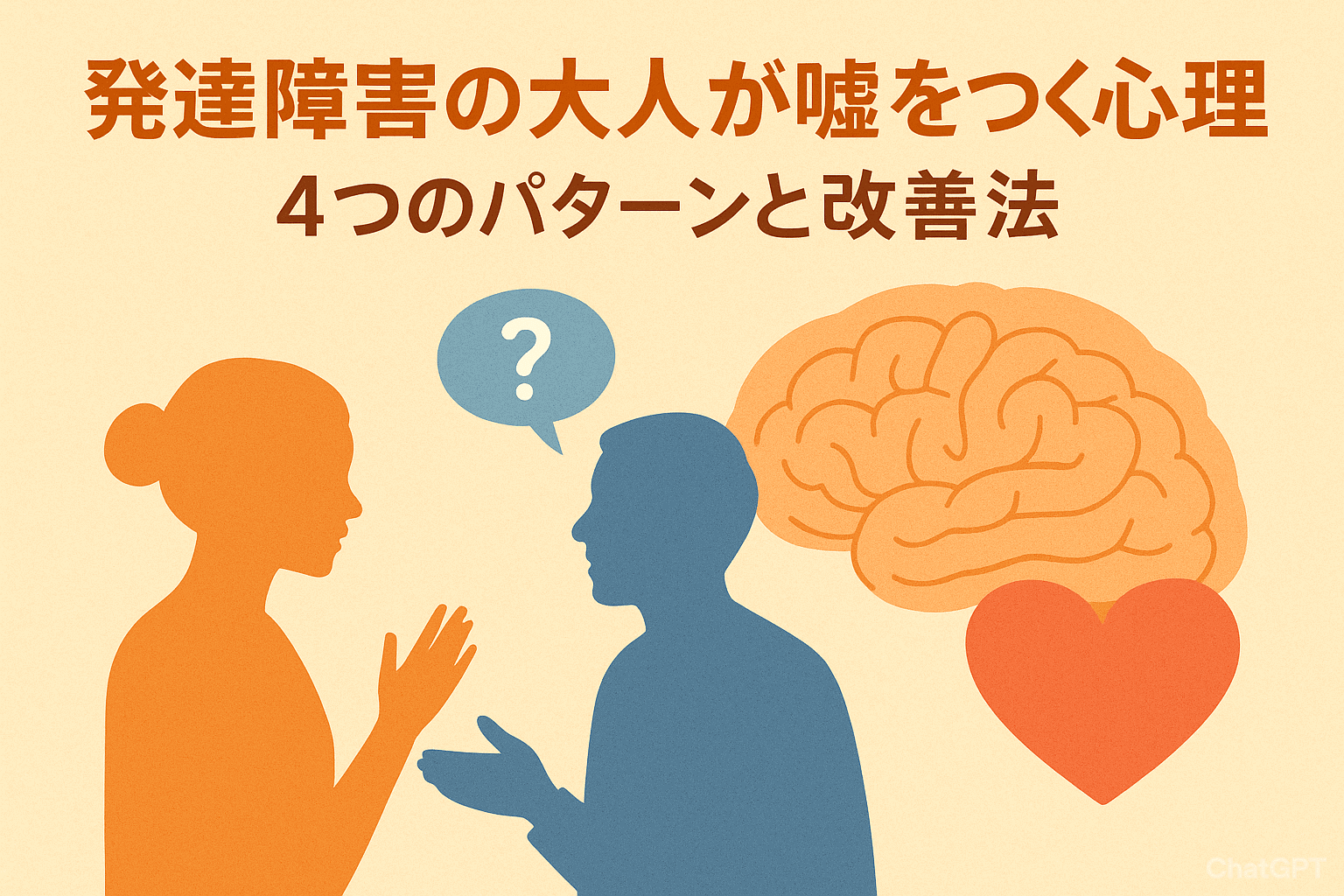こんなお悩みありませんか?
- 発達障害の家族や同僚が嘘をついているように感じて困っている
- 自分が発達障害で、つい嘘をついてしまうことがあり罪悪感を感じている
- 発達障害と嘘つきは関係があるの?本当のことを知りたい
この記事で分かること
✅ 発達障害の大人が嘘をついてしまう本当の理由(脳科学的根拠つき)
✅ 嘘をつく背景にある4つのパターンと心理メカニズム
✅ 今日から実践できる具体的な対処法と改善ステップ
🌟 この記事を読めば、あなたは発達障害と嘘の関係を正しく理解し、当事者も周囲の人も互いを理解し合える関係を築くための具体的な方法を手に入れることができます。
「初めてこのブログをお読みの方は、
**[【はじめまして】福祉のプロ×当事者が始める理由]**
で運営者の詳しいプロフィールと、なぜこのブログを始めたのかをご紹介しています。」
👤 この記事を書いている人

🏥 専門職として: 社会福祉士・精神保健福祉士の資格を持ち、福祉の現場で10年以上従事
💭 当事者として: ADHD・ASDの診断を受け、自身も「嘘つき」と言われた辛い経験を持つ
専門知識と実体験の両方から、あなたに寄り添いながら解説します。
📂 カテゴリー別記事一覧
🏛️ 社会保障制度 | 💼 福祉のお仕事 | 🧠 障害と生きづらさ
本記事は資格を持つ専門職の知識と個人の体験談に基づく情報提供です。医学的診断や治療の代替となるものではありません。
1. 発達障害の大人が嘘をつく脳科学的理由
💡 結論:発達障害の大人が嘘をつくのは「悪意」ではなく「脳の特性」です
発達障害の方の「嘘」は、実は以下の脳の特性が大きく関係しています:
🧭 認知処理の特性による「記憶のズレ」
| 脳の部位 | 役割 | 発達障害での影響 | 結果として起こること |
|---|---|---|---|
| 前頭前野 | 判断・抑制・計画 | 衝動的な発言をしやすい | 「確認せずに答える」 |
| 海馬 | 記憶の整理・保存 | 時系列や詳細があいまい | 「昨日と一昨日が混乱」 |
| ワーキングメモリ | 作業記憶 | 容量が少ない | 「話しながら内容が変化」 |
🛡️ 感情・社会性の特性による「防御反応」
⚡ ADHDの特性
- 衝動性: 考える前に答えてしまう
- 注意の偏り: 重要な詳細を見落とす
- 時間感覚の曖昧さ: 「いつ」の記憶が不正確
🔄 ASDの特性
- 変化への不安: 予想外の質問にパニック状態
- 社会的想像力の困難: 相手の期待を読み違える
- パターン化思考: 「いつもの返答」で乗り切ろうとする
【関連記事】発達障害についての関連記事こちらもご覧ください⇩
発達障害とは?大人の特徴を当事者目線で分かりやすく解説
📊 統計データで見る実態
調査結果(発達障害者支援センター調べ)
- 発達障害の診断を受けた成人の 約74% が「事実と異なる発言」を経験
- 特に 職場・学校 など評価される場面で起こりやすい(85%)
- 幼少期からの叱責経験 が多い方ほど頻度が高い傾向
💡 ポイント:これは「嘘つき」の問題ではなく、「認知特性」の問題なのです。
2. 発達障害の大人が嘘をついてしまう4つのパターンと対処法
パターン1:記憶の混乱による事実誤認
🔍 具体例
- 「昨日提出しました」→ 実は一昨日だった
- 「3回連絡しました」→ 実は1回だった
- 「聞いていません」→ 実は聞いたが忘れた
⚙️ メカニズム
海馬の記憶整理機能の特性により、時系列や頻度の記憶が曖昧になる
🎯 対処法
- 記録の習慣化: スマホのメモ・カレンダー活用
- 確認の言葉: 「記憶が曖昧なので確認します」
- 視覚化: 重要な件は付箋やホワイトボードに記載
パターン2:防御的な嘘(怒られることへの恐怖)
🔍 具体例
- 「もうやりました」→ 実はまだ未完了(怒られるのが怖い)
- 「知らない」→ 知っているが説明に自信がない
- 「大丈夫です」→ 実は困っているが迷惑をかけたくない
⚙️ メカニズム
扁桃体の過敏な反応により、批判や叱責への恐怖が極度に強い
🎯 対処法
- 安全な環境作り: 「間違っても大丈夫」の雰囲気
- 段階的報告: 進捗を細かく共有する仕組み
- 感情の言語化: 「不安です」「困っています」と伝える練習
パターン3:相手思いの嘘(気遣いから生まれる配慮)
🔍 具体例
- 「楽しかったです」→ 実は疲れたが相手を傷つけたくない
- 「問題ありません」→ 実は困っているが心配させたくない
⚙️ メカニズム
相手の感情を想像して配慮しようとするが、適切な表現方法がわからない
🎯 対処法
- 感情の表現練習: 「疲れましたが、貴重な体験でした」など
- 境界線の設定: 自分の感情を大切にすることの重要性を理解
- 代替表現: 相手を傷つけずに本音を伝える方法を学習
パターン4:期待に応えたい嘘(承認欲求からくる誇張)
🔍 具体例
- 実績や能力の誇張
- 予定や計画を確定事項として話す
- 他人からの評価を過度に良く表現
⚙️ メカニズム
自己肯定感の低さから、相手に認められたい気持ちが強く働く
🎯 対処法
- 小さな成功体験: 達成可能な目標設定で自信を構築
- 事実ベースの報告: 「現在〇%完了」「予定では〇日」など
- 自己受容の練習: ありのままの自分を受け入れる
3. 私が「嘘つき」と言われた辛い経験と気づき
🌟 当事者の実体験:上司との信頼関係が崩れた出来事あ
📅 状況
入社3年目、重要なプロジェクトの進捗報告の際に起きました。
上司:「この資料、昨日の会議で説明したよね?」
私:「はい、説明しました」
→ 実際は一昨日の別会議での話で、後で発覚し大問題に
💔 その時の心境
- 記憶が本当に曖昧で自信がなかった
- 「覚えていない」と言ったら無責任だと思われそう
- 咄嗟に「安全そうな答え」を選んでしまった
- まさか「嘘つき」と思われるとは想像していなかった
😢 結果として起こったこと
- 上司からの信頼を大きく失った
- 「報告が信用できない」と言われ続けた
- 自分でも「また間違えるのでは」と不安が増大
🔄 転機:専門知識を学んで気づいた真実
💡 学んだこと
- これは「嘘」ではなく「認知特性」の問題だった
- 記憶の曖昧さは生まれつきの脳の特性
- 適切な対処法があることを知った
🛠️ 実践した改善方法
- スマホでの音声録音: 重要な会議は許可を得て録音
- メール・チャットでの確認: 「〇月〇日の△△の件でよろしいでしょうか?」
- 素直な言葉: 「記憶が曖昧なので確認させてください」
✨ 結果
- 上司との関係が徐々に改善
- 「確認してくれるから安心」と評価が変化
- 自分自身の罪悪感も軽減
🌈 当事者の皆さんに伝えたいこと
あなたは「嘘つき」ではありません。
脳の特性を理解し、適切な対処法を身につければ、必ず改善できます。
私も最初は辛い経験ばかりでしたが、今では:
- 職場で信頼される存在になれた
- 自分の特性を活かした働き方を見つけた
- 同じ悩みを持つ人の支援ができるようになった
4. 現場でよく見る事例と効果的なアプローチ
📋 よく相談される事例TOP3
🥇 1位:職場での報告・連絡・相談
- 「順調です」→ 実は大幅遅延
- 「理解しました」→ 実は全く分からない
- 「問題ありません」→ 実は深刻な課題が発生
🥈 2位:家庭での約束・責任
- 「掃除しました」→ 途中まで(本人的には「手をつけた=やった」)
- 「宿題終わった」→ 一部だけ完了
- 「連絡します」→ 忘れてしまう
🥉 3位:対人関係での感情表現
- 「大丈夫」→ 実は傷ついている
- 「楽しい」→ 実は疲れている
- 「分かる」→ 実は理解できていない
🎯 支援現場で効果的だったアプローチ
✅ 成功事例1:記録システムの導入
- before: 口約束で忘れる→「やったのに」論争
導入方法: 共有カレンダー・タスク管理アプリ
→after: 客観的な記録で認識の齟齬が激減
✅ 成功事例2:感情の言語化練習
- before: 「大丈夫」「問題ない」の多用
練習方法: 感情カードを使った表現練習
→after: 「疲れているけど頑張ります」など具体的な表現が可能に
✅ 成功事例3:段階的な報告システム
- before: 完了まで「順調」で通し、最後に破綻
システム: 25%、50%、75%の進捗報告
→after: 早期に問題発見・対処が可能
5. 【⚠️重要】知っておくべき注意点とデメリット
🚫 やってはいけない対応(周囲の方へ)
❌ 感情的に責める
- 「また嘘ついた!」「信用できない!」
→ 更に防御反応が強くなり悪循環
❌ 完璧を求める
- 「絶対に正確に言って」「100%確実にして」
→ 過度なプレッシャーで思考停止状態に
❌ レッテルを貼る
- 「○○さんは嘘つきだから」
→ 自己肯定感が下がり改善意欲も低下
⚠️ 改善の限界と現実的な期待値
時間がかかることを理解する
- 即効性はない: 最低でも3-6ヶ月の継続が必要
- 完全になくすのは困難: ストレス下では起こりやすい
- 長期的な視点: 「減らす」ことから始める
個人差が大きい
- 特性の現れ方は人それぞれ
- 効果的な方法も個人により異なる
- **trial and error(試行錯誤)**の姿勢が大切
6. 今日から始められる具体的改善ステップ
ステップ1:記録・確認の仕組み化
📱 デジタルツール活用法
- スマホのボイスメモ: 重要な話は即座に録音
- Googleカレンダー: 予定と実績を色分けで管理
- Todoistアプリ: タスクの進捗を%で記録
【関連記事】発達障害の人におすすめ、生き方が楽になった体験を記事にしています⇩
「発達障害 おすすめアプリ5選!3年使って効果があったツール【2025年版】」
💬 コミュニケーション改善
- 魔法の言葉: 「記憶が曖昧なので確認します」
- 事実ベース報告: 「現在50%完了、明日には80%予定」
- 感情の言語化: 「不安ですが頑張ります」
ステップ2:環境づくりと周囲への働きかけ
🏠 家庭環境
- 定期チェック時間: 毎日夕食後に進捗確認
- 視覚化: ホワイトボードでタスクを見える化
- 小さな成功を褒める: 正直に話せた時は必ず評価
🏢 職場環境
- 上司との定期面談: 週1回15分の進捗確認
- メール・チャット活用: 重要な指示は文字で残す
- 同僚の理解促進: 特性について適度に情報共有
ステップ3:自己理解と心のケア
🧘♀️ セルフケア
- ストレス管理: 深呼吸・軽い運動で不安軽減
- 自己受容: 「完璧でなくても価値がある」という意識
- 成功体験の記録: 改善できた事例をメモに残す
📚 継続的な学習
- 発達障害に関する正しい知識の習得
- 同じ悩みを持つ人のコミュニティ参加
- 専門機関への相談も選択肢の一つ
7. 【まとめ】発達障害の大人の嘘への対処法 今日から実践できる3つのポイント
1. 理解:「嘘」ではなく「認知特性」と捉える
🧠 脳科学的事実: 発達障害の大人が事実と異なることを言うのは、悪意ではなく海馬や前頭前野の特性によるものです。まずはこの理解から始めましょう。
2. 仕組み:記録と確認を習慣化する
📝 具体的な方法: スマホのメモ・音声録音を活用し、曖昧な記憶は「確認します」と答える。進捗は数値化して報告する仕組みを作りましょう。
3. 環境:安心して真実を話せる関係性を構築
💖 雰囲気作り: 「間違っても大丈夫」「一緒に解決しよう」という姿勢で接し、小さな正直さを褒める。感情的にならず事実確認を行いましょう。
💬 最後に:一緒に「生きやすさ」を見つけていきましょう
この記事が「発達障害の嘘について悩んでいる」という当事者の方や周囲の方の参考になれば嬉しいです。
🎯 次のアクション
- 今日から1つだけ、記事で紹介した方法を試してみてください
- 1週間後、どんな変化があったかを振り返ってみてください
- 1ヶ月継続できたら、新しい方法を追加してみてください
💌 あなたの体験も教えてください!
- **「この方法で改善できました!」**という成功体験
- **「こんなことで困っています」**というお悩み相談
- **「この部分をもっと詳しく知りたい」**というリクエスト
コメントやメッセージでお聞かせください😊 同じ悩みを持つ誰かの希望になるかもしれません。
📢 この記事が役に立ったら、ぜひSNSでシェアしてください!
一人でも多くの方に「あなたは嘘つきじゃない」ということを伝えていきましょう。