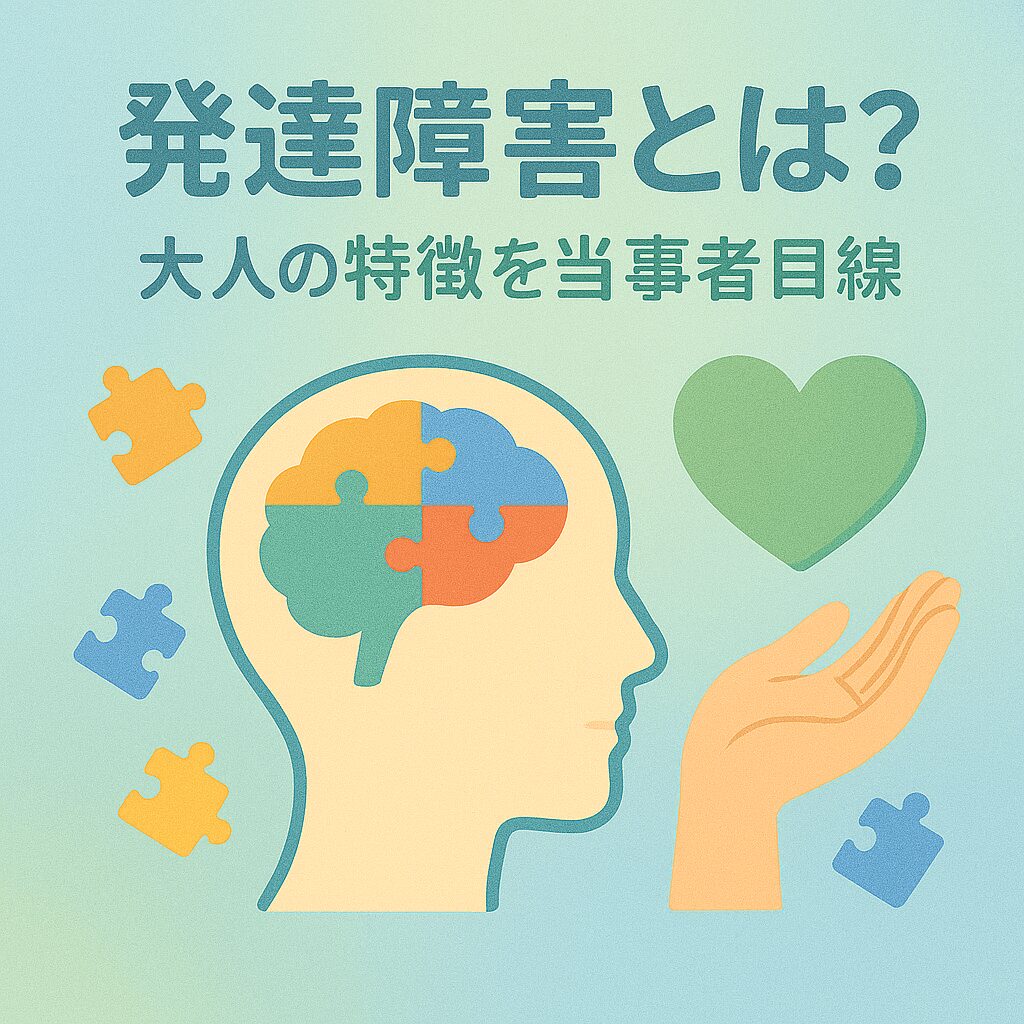こんなお悩みありませんか?
- 周りの人と何となく違う気がして困っている
- 「発達障害かもしれない」と思うけど、どんな特徴があるのか分からない
- 大人になってから発達障害って分かることがあるって聞いたけど、本当?
この記事で分かること
✅ 発達障害の基本的な仕組み・種類
✅ 大人の発達障害によく見られる特徴
✅ 実際に診断を受けた当事者の体験談・気づき
この記事を書いている人

福祉の専門職(社会福祉士・精神保健福祉士)で、
発達障害(ADHD・ASD)の当事者でもあるバッキーが、専門知識と実体験の両方から解説します。
「初めてこのブログをお読みの方は、
**[【はじめまして】福祉のプロ×当事者が始める理由]**
で運営者の詳しいプロフィールと、なぜこのブログを始めたのかをご紹介しています。」
📂 カテゴリー別記事一覧
🏛️ 社会保障制度 | 💼 福祉のお仕事 | 🧠 障害と生きづらさ
※本記事は社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・保育士の資格を持つ私の実体験や専門知識、福祉制度の理解に基づく情報提供です。医学的診断や治療の代替となるものではありません。
1. 【基本編】発達障害とは?中学生でも分かる基礎知識
簡単に言うと、発達障害は「脳の働き方の違い」です
発達障害は病気ではありません。生まれつきの脳の機能の違いによって、日常生活や学習、仕事などで困りごとが生じる状態のことです。
なぜこの障害があるの?
発達障害は決して珍しいものではありません。文部科学省の調査では、小中学生の約8.8%に発達障害の可能性があるとされています。つまり、クラスに2〜3人はいる計算になります。
主な発達障害の種類
📋 3つの主要なタイプ
| 障害名 | 主な特徴 | 割合 |
|---|---|---|
| ADHD(注意欠如・多動性障害) | 注意力散漫、衝動的、じっとしていられない | 約3-5% |
| ASD(自閉スペクトラム症) | コミュニケーションの困難、こだわりが強い | 約1% |
| LD(学習障害) | 読む・書く・計算などの特定分野が苦手 | 約2-3% |
💡 ワンポイント解説
実際には複数の特性を併せ持つ人も多くいます。私自身もADHDとASDの両方の診断を受けています。一番怖いのはそれによる二次障害です。生きづらさからうつ病や不安症などの精神疾患になりやすいのが特徴です。
2. 【詳細編】大人の発達障害によく見られる特徴
ADHD(注意欠如・多動性障害)の大人の特徴
🎯 注意力に関する特徴
- 会議中に集中できず、他のことを考えてしまう
- 約束や締切を忘れやすい
- 整理整頓が苦手で、デスクや部屋が散らかりがち
- 優先順位をつけるのが困難
⚡ 衝動性・多動性の特徴
- 相手の話を最後まで聞かずに返事をしてしまう
- 思いついたらすぐ行動してしまう
- 長時間座っていると落ち着かない
- 貧乏ゆすりなどの小さな動きが止められない
ASD(自閉スペクトラム症)の大人の特徴
💬 コミュニケーションの特徴
- 相手の表情や雰囲気から気持ちを読み取るのが苦手
- 冗談や皮肉が理解できないことがある
- 「空気を読む」ことが難しい
- 電話での会話が苦手
🔄 こだわり・感覚の特徴
- 決まったルーティンを崩されると不安になる
- 特定の分野に強い興味・関心を持つ
- 音や光、触感に敏感
- 変化や予定変更が苦手
LD(学習障害)の大人の特徴
📝 読み書きの困難
- 文章を読むのに時間がかかる
- 漢字を覚えるのが苦手
- 文字を書くときのバランスが悪い
🔢 計算の困難
- 暗算が苦手
- 数字の桁を間違えやすい
- 時間やお金の計算でミスが多い
3. 【体験談】実際に診断を受けた/関わった経験
🌟当事者としての体験
診断を受けるまでの道のり
30歳を過ぎてから診断を受けました。それまでは「自分はダメな人間だ」「努力が足りないんだ」と自分を責め続けていました。
実際に困っていたこと
- 職場で同じミスを繰り返してしまう
- 人との会話で「なんか違う」と感じることが多い
- 疲れやすく、一日の終わりにはぐったり
- 感情のコントロールが難しい
診断を受けて良かったこと
- 「性格の問題」ではなく「脳の特性」だと分かって安心した
- 具体的な対処法を学べるようになった
- 同じような悩みを持つ人とつながることができた
🌟支援者としての視点
現場でよく見る事例
福祉の現場で働いていて気づくのは、大人になってから発達障害に気づく人の多さです。特に以下のようなタイミングで相談に来られる方が多いです。
相談のきっかけ
- 就職・転職での困難:何度も職場を変わっている
- 結婚・出産のタイミング:パートナーや子どもとの関係で困りごと
- 子どもの診断:お子さんの発達障害が分かった時に親も気づく
スムーズに進めるコツ
- まずは信頼できる人(家族・友人・専門職)に相談
- 発達障害者支援センターなど公的機関を活用
- 一人で抱え込まず、段階的にサポートを求める
実際に障害者手帳を取得した体験談はこちらで詳しく書いています:
→ 【実体験】発達障害で障害者手帳を取得した理由とメリット5つ
4. 【注意点・デメリット】知っておくべきこと
診断を受ける際の注意点
⚠️ よくある勘違い
- 「発達障害の診断を受けたら人生終わり」
→ 実際は適切なサポートを受けられるようになります - 「薬を飲まなければいけない」
→ 薬物療法は選択肢の一つで、必須ではありません - 「治る・治らない」
→ 発達障害は「治す」ものではなく「特性と上手に付き合う」ものです
職場での配慮について
🏢 合理的配慮の例
- 指示は口頭ではなく文書でもらう
- 静かな環境で作業できる場所の確保
- 業務の優先順位を明確にしてもらう
💼 注意すべきポイント
- すべての職場で理解があるわけではない
- 配慮を求めることで関係性が変わる可能性
- 自分自身の特性理解が重要
5. 【まとめ】今日から使える3つのポイント
1. 自分の特性を知ることから始めよう
まずは「困りごと」を具体的に書き出してみましょう。パターンが見えてくるはずです。
2. 一人で悩まず、信頼できる人に相談を
発達障害者支援センターや精神保健福祉センターなど、無料で相談できる場所があります。
3. 「ダメな自分」ではなく「特性を持つ自分」として受け入れる
発達障害は個性の一つです。適切なサポートがあれば、強みとして活かすことも可能です。
💬最後に
この記事が「もしかして発達障害かも?」と思っている方の参考になれば嬉しいです。
あなたの体験も教えてください!
- 実際に診断を受けた方の体験談
- 「こんなことで困っている」というお悩み
- 「この部分をもっと詳しく知りたい」というリクエスト
コメントやメッセージでお聞かせください😊 一緒に「生きやすさ」を見つけていきましょう!
参考文献・リンク
- 厚生労働省「発達障害者支援法について」
- 文部科学省「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」
- 発達障害情報・支援センター(国立障害者リハビリテーションセンター)