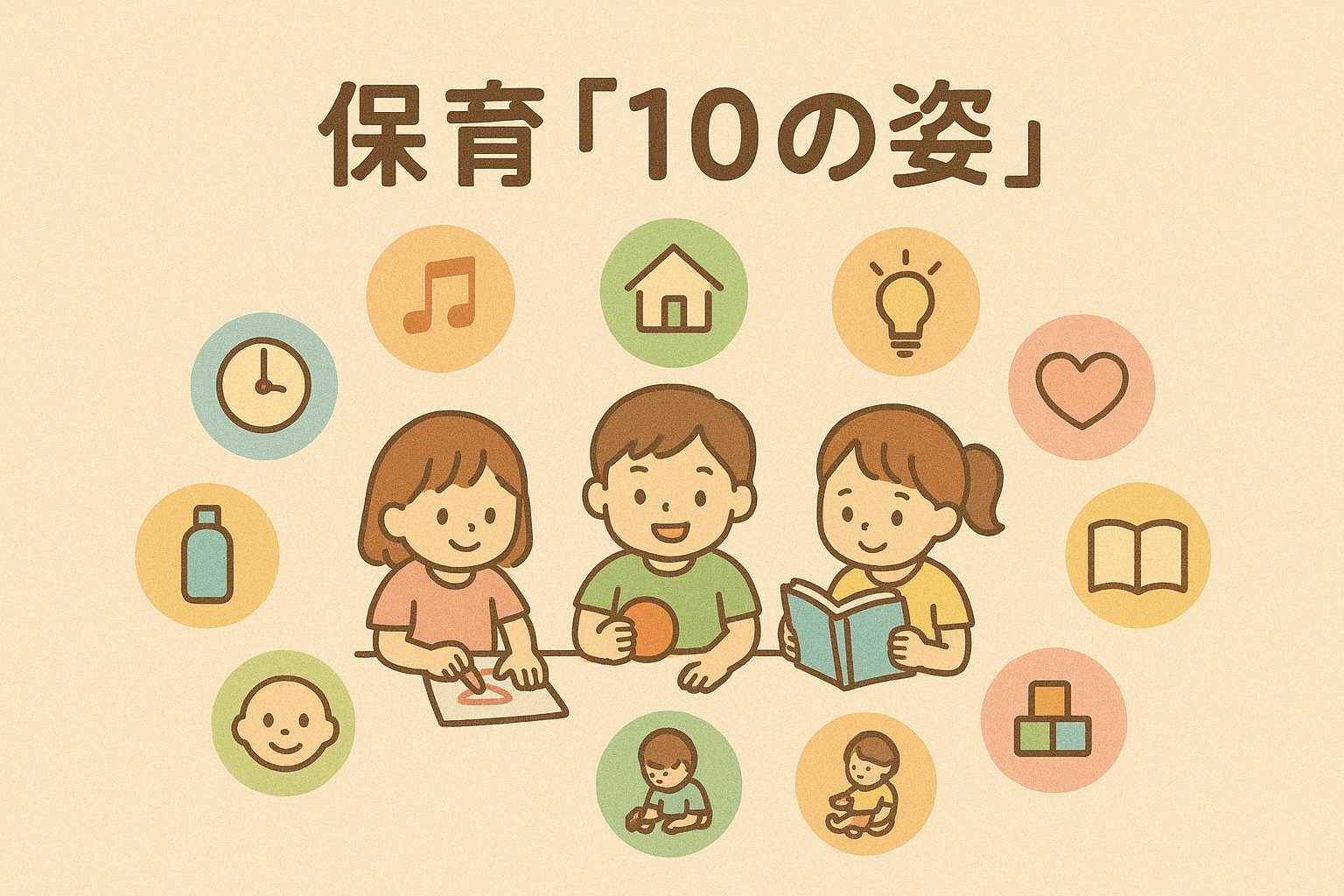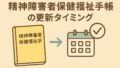こんなお悩みありませんか?
- 保育の「10の姿」って聞いたことはあるけど、実際何のことかよく分からない
- 子どもの成長を見る時に、どこに注目すればいいか分からない
- 保育要領に書いてある「10の姿」の具体例を知りたい
- 我が子の成長を「10の姿」で理解したい
この記事で分かること
✅ 保育「10の姿」の基本的な仕組み
✅ 10項目それぞれの具体的な例と見方
✅ 実際の保育現場での活用体験談・注意点
「初めてこのブログをお読みの方は、
**[【はじめまして】福祉のプロ×当事者が始める理由]**
で運営者の詳しいプロフィールと、なぜこのブログを始めたのかをご紹介しています。」
この記事を書いている人

福祉の専門職(保育士・社会福祉士)として保育現場で働いた経験があり、現在は子育て支援センターを利用しながら自身の子育てにも奮闘中の私が、専門知識と実体験の両方から「10の姿」について分かりやすく解説します。保育者としての視点と、実際に子育てをしている保護者としての視点を織り交ぜてお伝えします。
📂 カテゴリー別記事一覧
🏛️ 社会保障制度 | 💼 福祉のお仕事 | 🧠 障害と生きづらさ
※本記事は社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・保育士の資格を持つ私の実体験や専門知識、福祉制度の理解に基づく情報提供です。医学的診断や治療の代替となるものではありません。
1. 【基本編】保育「10の姿」とは?中学生でも分かる基礎知識
簡単に言うと、「10の姿」は「子どもの成長を見る10の窓」です
保育所保育指針や幼稚園教育要領に示された「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」のことを「10の姿」と呼びます。これは小学校入学前の5歳児クラス(年長さん)の子どもたちが、どんな力を身につけて欲しいかを10項目にまとめたものです。
なぜこの「10の姿」があるの?
| 理由 | 詳細説明 |
|---|---|
| 統一的な視点 | 全国どこでも同じ基準で子どもの成長を見守れる |
| 小学校との連携 | 小学校の先生にも子どもの育ちを伝えやすくなる |
| 保護者との共有 | 家庭でも同じ視点で子育てができる |
| 個別支援の充実 | 一人ひとりの特性に合わせた支援ができる |
誰が利用するの?
- 保育士・幼稚園教諭:日々の保育計画や評価に活用
- 保護者:家庭での子育ての参考として
- 小学校の先生:入学してくる子どもたちの理解のために
- 子育て支援に関わる人:専門的な視点での子ども理解のために
2. 【詳細編】保育「10の姿」の具体的な内容と見方
📊 「10の姿」一覧表
| 項目 | 姿の名称 | キーワード |
|---|---|---|
| ① | 健康な心と体 | 体力・安全・生活習慣 |
| ② | 自立心 | 身の回りのこと・意欲・責任感 |
| ③ | 協同性 | 友達との協力・共通目標 |
| ④ | 道徳性・規範意識の芽生え | ルール・善悪・相手の気持ち |
| ⑤ | 社会生活との関わり | 家族・地域・文化・伝統 |
| ⑥ | 思考力の芽生え | 考える・試す・工夫 |
| ⑦ | 自然との関わり・生命尊重 | 動植物・環境・生命の大切さ |
| ⑧ | 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚 | 数・形・文字への興味 |
| ⑨ | 言葉による伝え合い | 話す・聞く・相手に合わせる |
| ⑩ | 豊かな感性と表現 | 美しさ・芸術・創造性 |
保育「10の姿」各項目の具体例
🏃♀️ ①健康な心と体
| 場面 | 具体的な子どもの姿 |
|---|---|
| 🌞 朝の活動 | 「疲れたから少し休む」と自分で判断できる |
| 🧼 生活習慣 | 手洗い・うがいを意識して行う |
| ⚽ 運動遊び | 友達と一緒に思いっきり体を動かして遊ぶ |
| 🛌 睡眠 | 早寝早起きの大切さを理解している |
💭 こんな姿が見られたら…
体調管理や基本的生活習慣が身についてきた証拠です!
🌱 ②自立心
「自分でやりたい!」気持ちを大切に
✨ 日常生活での自立心
- 自分でできることは最後までやり遂げようとする
- 「これは僕の仕事だから」と責任感を持って取り組む
🙋♀️ コミュニケーション面
- 困った時は「手伝って」と自分から言える
- 新しいことにも「やってみたい!」と挑戦する
🤝 ③協同性
👥 グループ活動での姿
├─ 運動会:「みんなで勝とう!」と声をかけ合う
├─ 制作活動:積み木で大きな作品を作る時に役割分担
├─ 困った友達:「一緒にやろう」と声をかける
└─ 意見の違い:話し合いで解決しようとする
🎯 ポイント:一人ではできないことも、みんなでなら達成できる喜びを知る
⚖️ ④道徳性・規範意識の芽生え
| 💡 ルール理解 | 💝 思いやり |
|---|---|
| 「順番を抜かしたらいけないよね」 | 「ごめんね、痛かったよね」と謝る |
| 約束を守ろうとする | 「困ってる人がいたら助けてあげよう」 |
🌟 内面の成長:嘘をついた時に「本当のことを言わなきゃ」と気づく心の動き
🏘️ ⑤社会生活との関わり
🎌 文化・伝統
- 「お正月にはお雑煮を食べるんだ」と文化を理解する
- 地域のお祭りに参加して楽しむ
👨👩👧👦 家族・地域
- 近所の人に「おはようございます」と挨拶する
- 「お父さんはお仕事、私は保育園」と家族の役割を理解
🧠 ⑥思考力の芽生え
「なぜ?」「どうして?」の好奇心が育つ時期
🔍 疑問・発見
- 「なんで雨が降るんだろう?」と疑問を持つ
- 「昨日より今日の方が暖かいね」と気づく
🔧 工夫・予想
- 積み木が倒れた時「こうしたら倒れないかも」と工夫する
- パズルで「この形はここに入りそう」と予想してから試す
🌿 ⑦自然との関わり・生命尊重
🦋 生き物への関心
- 「蝶々が羽を怪我してる、かわいそう」と生き物を心配する
- 虫を見つけても「踏んじゃだめ、生きてるもん」と命を大切にする
🌱 植物・自然現象
- 花に水をあげながら「大きくなあれ」と声をかける
- 「雨の音っていろんな音がするね」と自然現象に興味を示す
🔢 ⑧数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚
| 分野 | 具体例 |
|---|---|
| 数量 | 「みんなで5人だから、お皿も5枚だね」と数を数える |
| 文字・記号 | 「この標識、前も見たことある!」と興味を示す |
| 図形 | 「○と△を組み合わせると顔みたい」と形で遊ぶ |
| 文字認識 | 自分の名前を見つけて「あ、これ僕の名前だ!」と喜ぶ |
💬 ⑨言葉による伝え合い
📢 相手に合わせたコミュニケーション
- 相手が小さい子→「ゆっくり」話す
- 大人が相手→「丁寧に」話す
📖 話す・聞くスキル
- 「今日ね、公園で…」と順序立てて出来事を伝える
- 友達の話を最後まで聞いてから「そうなんだ」と反応する
- 「どういう意味?」と分からない言葉を質問する
🎨 ⑩豊かな感性と表現
🎵 音楽 → 「この音楽聞くと踊りたくなる!」
🌅 美術 → 「夕日がオレンジ色できれい」
🏺 造形 → 粘土で「これはママの顔」と想像したものを作る
🎨 感情表現 → 「悲しい時は青い色で描きたくなる」
✨ 表現の多様性:言葉だけでなく、体・色・形で気持ちを表現する豊かさ
💡ワンポイント解説
専門職として気づいたポイント:
「10の姿」は完璧に全部できることを求めているのではありません。一人ひとりの子どもが持つ「その子らしさ」を大切にしながら、これらの姿への「芽生え」や「育ち」を見つめることが重要です。
当事者として実感したこと:
我が子を見る時も、「できてない」ことに焦点を当てるのではなく、「今日はこんな成長があった!」という視点で見ると、子育てがもっと楽しくなります。
3. 【体験談】実際の保育現場での「10の姿」活用経験
🌟支援者としての視点
保育現場では、子ども一人ひとりの成長を「10の姿」の視点で観察し、記録しているところもあります。ここでは実際に私が担当した子どもたちの事例を、「10の姿」の番号を使って紹介します。
(※番号は前章で説明した10項目の姿を表しています)
ケース1:Aちゃん(5歳)の場合
Aちゃんは人前で話すのが苦手でしたが、絵を描くことが大好きでした。
観察のポイント:
- ⑩豊かな感性と表現:自分の気持ちを絵で表現できる
- ②自立心:好きなことには集中して取り組める
- ⑨言葉による伝え合い:絵を通じて友達とコミュニケーションを取る
結果:Aちゃんの「表現する力」を認めることで、徐々に自信を持って発表もできるようになりました。
ケース2:男の子グループの砂場遊び
「大きなお城を作ろう!」というプロジェクトが1週間続きました。
見られた「10の姿」:
- ③協同性:役割分担をして協力
- ⑥思考力の芽生え:「水を混ぜると固くなる」という発見
- ④道徳性・規範意識:「小さい子が壊しちゃっても怒らない」というルール作り
🌟当事者(発達障害)としての体験
私自身、ADHD(注意欠陥多動性障害)の診断を受けており、子どもの頃から「みんなと違う」感覚を持って育ちました。その経験から、「10の姿」を現在の視点で振り返ってみます。
私の子ども時代の特徴:
- ①健康な心と体:体を動かすことは大好きだったが、集中力が続かない
- ②自立心:興味のあることには人一倍取り組むが、苦手なことは避けがち
- ③協同性:一人遊びが好きで、グループ活動は苦手
- ⑥思考力の芽生え:「なぜ?」「どうして?」の質問が止まらない
- ⑩豊かな感性と表現:想像の世界に没頭するのが得意
発達障害についての関連記事こちらもご覧ください⇩
発達障害とは?大人の特徴を当事者目線で分かりやすく解説
現在の理解:
当時の私は「協同性」や「規範意識」の部分で苦労していましたが、それは「発達の遅れ」ではなく「発達の特性」でした。今思えば、私なりの「10の姿」があったのだと思います。
保育者になって気づいたこと:
「10の姿」は決して画一的な基準ではなく、一人ひとりの子どもの個性や特性を理解するための「ものさし」として使うべきだということです。私のような発達障害の子どもでも、その子らしい方法で「10の姿」は育まれていくのです。
🌟保護者との連携で大切にしていること
子育て支援センターを利用する中で、他の保護者の方々からよく受ける質問があります。保育士としての知識と、現在子育て中の保護者としての経験から、こんな風にお答えしています。
よくある保護者からの質問:
「うちの子、まだ字が読めないんです。大丈夫でしょうか?」

私の回答:
「⑧数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚は、『読める』『書ける』ことが目標ではありません。『看板の字を見て「あ、これ○○って書いてあるね」と興味を示したり、自分の名前を探そうとしたり』する姿が見られれば十分です。焦る必要は全くありませんよ。」
4. 【注意点・デメリット】知っておくべきこと
利用時の注意点
❌やってはいけないこと
- チェックリスト的な使い方:「できる・できない」で○×をつける
- 他の子との比較:「○○ちゃんはできるのに、なぜうちの子は…」
- 無理やり当てはめる:子どもの行動を無理に「10の姿」に分類する
⭕正しい活用方法
- 成長の過程を見る:今日の小さな変化や成長に注目
- その子らしさを大切に:一人ひとりの個性と発達のペースを尊重
- 総合的に見る:10項目は相互に関連し合っているものとして理解
よくある勘違い
| 勘違い | 正しい理解 |
|---|---|
| 小学校入学前に全部できないといけない | 「芽生え」が見られれば十分 |
| 10項目すべて平均的に育つもの | 得意分野から他の分野へ広がっていく |
| 家庭で特別な教育が必要 | 日常生活の中で自然に育まれる |
デメリット・制限事項
- 評価の難しさ:主観的な判断になりがちで、保育者の経験や視点に左右される
- 文書化の負担:詳細な記録を残そうとすると時間がかかる
- 保護者の不安:知識が不十分だと「うちの子は大丈夫?」と心配になる場合がある
5. 【まとめ】保育「10の姿」を活用する3つのポイント
📌今日から使える実践ポイント
1. 「できた・できない」ではなく「育ち」に注目する
子どもの行動を見る時は、「今日はこんな成長があった」「昨日よりもこんなことができるようになった」という視点を大切にしましょう。
2. 日常生活の中で「10の姿」を見つける
特別なことをする必要はありません。お手伝い、友達との遊び、食事の時間など、普段の生活の中にたくさんの学びと成長があります。
3. 子どもの「今」を大切にする
小学校準備のためだけでなく、今この瞬間の子どもの気持ちや興味を大切にすることが、結果的に豊かな成長につながります。
📊「10の姿」の関係性
①健康な心と体
↑↓
②自立心 ←→ ③協同性
↑↓ ↑↓
④道徳性・規範意識 ←→ ⑤社会生活との関わり
↑↓ ↑↓
⑥思考力の芽生え ←→ ⑦自然との関わり
↑↓ ↑↓
⑧数量・図形・文字への関心 ←→ ⑨言葉による伝え合い
↑↓
⑩豊かな感性と表現
すべての姿は相互に関連し、影響し合いながら育っていきます
💬最後に
この記事が「保育の10の姿について知りたい」「子どもの成長をどう見守ったらいいか分からない」という方の参考になれば嬉しいです。
「10の姿」は子どもたちの豊かな成長を支援するためのツールです。完璧を求めるのではなく、一人ひとりの子どもの「今」を大切にし、その子らしい成長を温かく見守っていくことが何よりも重要です。
子育て支援についての関連記事こちらもご覧ください⇩
子育て世帯必見!知らないと損する教育費支援制度の賢い使い方
あなたの体験も教えてください!
- 実際にお子さんの成長で「これって○番目の姿かな?」と思った体験談
- 「この部分をもっと詳しく知りたい」というリクエスト
- 「こんなことで困っている」というお悩み
コメントやメッセージでお聞かせください😊 一緒に子どもたちの「生きる力」を育んでいきましょう!