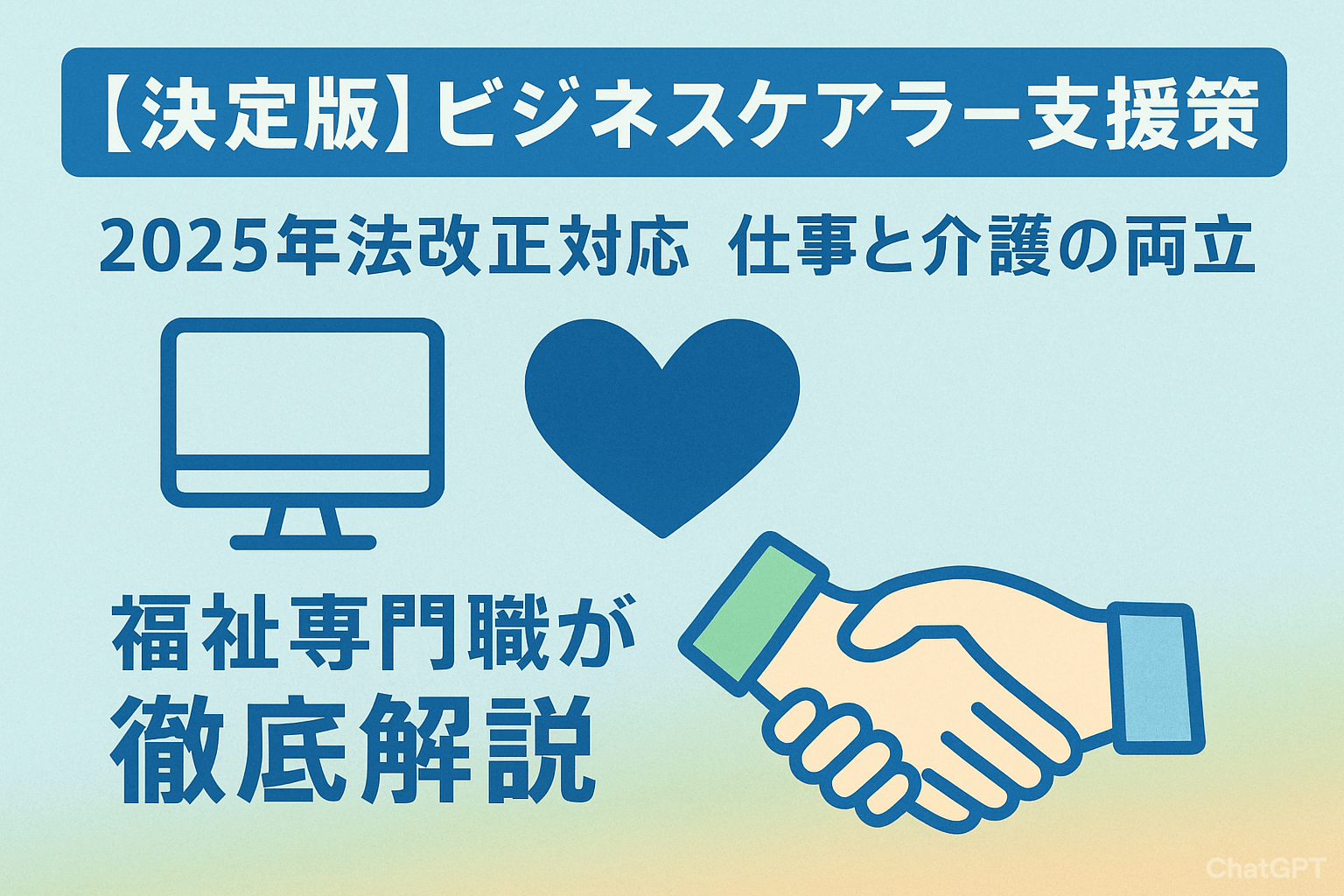こんなお悩みありませんか?
- 仕事をしながら家族の介護をしているけれど、どんなビジネスケアラー支援策があるか分からない
- 介護離職を考えているが、他にどのような支援制度があるのか知りたい
- 企業がビジネスケアラーにどんなサポートをしてくれるのか詳しく知りたい
- 2025年の法改正で何が変わるのか理解したい
仕事をしながら家族の介護をしているあなたへ。
この記事では、福祉の専門家がビジネスケアラー支援策について、2025年の法改正でどう変わるかを含め、仕事と介護を両立するための支援制度を徹底解説します。
この記事で分かること
✅ ビジネスケアラー支援策の基本的な仕組みと種類
✅ 2025年育児・介護休業法改正の具体的な内容と支援制度への影響
✅ 厚生労働省・経済産業省が推進する国・企業・個人レベルの支援制度
✅ 実際にビジネスケアラーとして働く当事者の体験談と支援者からの実践的アドバイス
この記事を読めば、あなたは仕事と介護の両立に必要なビジネスケアラー支援策を理解し、介護離職せずに安心して働き続けるための具体的な道筋が見えてきます。
「初めてこのブログをお読みの方は、
**[【はじめまして】福祉のプロ×当事者が始める理由]**
で運営者の詳しいプロフィールと、なぜこのブログを始めたのかをご紹介しています。」
この記事を書いている人

福祉の専門職(社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・保育士)で、発達障害の当事者でもあるバッキーが、専門知識と実体験の両方から解説します。また、祖母の介護体験を通じて、当事者としての視点も持っています。
📂 カテゴリー別記事一覧
🏛️ 社会保障制度 | 💼 福祉のお仕事 | 🧠 障害と生きづらさ
※本記事は社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・保育士の資格を持つ私の専門知識と個人の体験談に基づく情報提供です。医学的診断や治療の代替となるものではありません
1. 【基本編】ビジネスケアラー支援策とは?働きながら介護する人への基礎知識
ビジネスケアラー支援策とは
ビジネスケアラー支援策とは簡単に言うと「仕事をしながら介護をする人を支える制度」です
ビジネスケアラーとは、家族の介護をしながら仕事を続けている従業員のことです。
2030年時点では約318万人に上り、経済損失額は約9兆円と試算されています。
ビジネスケアラー支援策は、この問題を解決するために厚生労働省や経済産業省、企業が連携して用意している様々な支援制度のことを指します。介護休業、介護休暇、短時間勤務、フレックスタイム、テレワーク制度などが含まれます。
なぜこの支援制度・サービスがあるの?
ビジネスケアラー支援策が重視される主な理由は以下の3つです:
- 労働力不足の防止:2025年に団塊の世代が75歳以上の後期高齢者に突入し、それに伴い生産年齢が減少するため、働ける人への支援が必要です
- 経済的損失の防止:介護離職による経済損失を防ぐため、地域包括支援センターとの連携も含めた包括的な支援が求められています
- 個人の生活の質向上:介護と仕事の両立で生じる身体的・精神的負担を軽減するため
誰が利用できるの?
利用対象者は幅広く設定されています:
- 現在家族の介護をしている従業員
- 将来的に介護が必要になる可能性がある従業員
- 企業(従業員支援のための制度導入)
- 介護サービス事業者
【関連記事】家族の世話で困っている若者を助ける仕組みも詳しく紹介しています⇩
ヤングケアラー支援の第一歩。「助けて」が言えないあなたへ、社会福祉士が教える相談のヒント
2. 【詳細編】ビジネスケアラー支援策の具体的な内容・申請手順
🏢 企業レベルのビジネスケアラー支援策
ステップ1:実態把握と環境整備
まずはビジネスケアラー支援策に関する企業内の実態を把握しましょう。
介護と仕事の両立に関して、従業員へのアンケートやヒアリングで調査を実施します。
ステップ2:支援制度の導入・拡充
- 介護休業制度の拡充:法定を上回る期間や給与保障の設定
- フレックスタイム制度の導入:柔軟な働き方を可能にする
- テレワーク制度の充実:在宅での介護サポートを支援
- 介護支援金の支給:経済的負担の軽減
- 相談窓口の設置:専門的なアドバイス提供
ステップ3:従業員への情報提供・研修
- 介護制度に関する研修実施
- 相談窓口の周知
- 介護サービス情報の提供
🏛️ 国によるビジネスケアラー支援策
2025年4月施行:育児・介護休業法改正の主なポイント
厚生労働省による介護離職防止のための主な改正内容:
| 改正項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 情報提供義務化 | 企業による両立支援制度の情報提供が義務となる |
| 研修・相談義務化 | 研修・相談窓口設置が企業に義務付けられる |
| 介護休暇柔軟化 | 介護休暇制度の利用がより柔軟になる |
| ガイドライン策定 | 仕事と介護の両立支援ガイドラインを策定 |
経済産業省は「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」を公表し、企業のビジネスケアラー支援策の取り組みを促進しています。
👤 個人レベルで利用できるビジネスケアラー支援
既存の支援制度
主な制度一覧:
- 介護休業:最大93日間(介護者一人につき)- 長期間の介護に対応
- 介護休暇:年5日間(要介護者2人以上の場合10日間)- 短期間の介護ニーズに対応
- 短時間勤務制度:1日の労働時間の短縮 – 継続的な働き方調整
- 残業免除制度:時間外労働の免除 – 介護時間の確保
- 介護サービス:地域包括支援センターを通じた相談・申請 – 専門的サポート
【関連記事】介護保険について詳しく記事にしています⇩
介護保険制度とは?40歳未満でも知っておく理由
💡 専門家のワンポイント解説
専門職として多くのケースを見てきましたが、「ビジネスケアラー支援策があることを知らない」という方が非常に多いです。
また当事者として感じるのは、制度を知っていても「使いにくい雰囲気」がある職場も少なくないということです。まずは人事部や上司、そして地域包括支援センターに相談することから始めてみてください。
3. 【体験談】実際に使ってみた/関わった経験
🌟 当事者としての体験
私自身も祖母の介護経験がありますが、当時は今ほど制度が認知されておらず、また職場での前例もなかったため、結果的に制度を利用することができませんでした。
実際の状況:
- 介護休暇制度があることは知っていましたが、職場で利用した人が誰もいない状況
- 「迷惑をかけてしまうのではないか」という後ろめたい気持ちが強く、申請に踏み切れませんでした
- 制度の存在は知っていても、実際に使える雰囲気ではなかったのが正直なところです
困ったこと・後悔していること:
- 困ったこと:制度があっても「使いにくい空気感」があり、一人で抱え込んでしまった
- 後悔:もっと積極的に人事部に相談すれば良かった。祖母にもっと寄り添えたかもしれません
- 感じたこと:当時は「仕事か介護か」の二択で考えがちでしたが、両立できる道があったはずです
「あの時知っていれば…」と思うポイント:
- 地域包括支援センターに相談すれば、職場への働きかけ方も教えてもらえたかもしれない
- 同じような状況の人とつながる方法があったこと
- 「前例を作る」ことの大切さ – 後に続く人のためにもなること
🌟 支援者としての視点
社会福祉士として多くのビジネスケアラーの相談に乗ってきました。
現場でよく見る事例:
- 抱え込み型:「会社に迷惑をかけたくない」と一人で抱え込む(私もまさにこのパターンでした)
- 情報不足型:制度があることを知らずに離職を考える
- 前例不安型:制度は知っているが「職場で前例がない」ことを理由に利用を諦める
- 罪悪感型:「後ろめたい気持ち」で制度利用に踏み切れない
利用者さんが躓きやすいポイント:
- 制度の存在を知らない
- 知っていても「使いにくい雰囲気」を感じて諦める
- 職場での前例がないことへの不安
- 申請手続きが分からない
- 周囲への罪悪感や後ろめたさ
スムーズに進めるコツ:
- 勇気を出して最初の一歩を:私のように後悔しないよう、まずは人事部に相談してみてください
- 「前例を作る」意識を持つ:あなたの行動が後に続く同僚の道を開きます
- 早めの相談:問題が深刻化する前に専門家に相談
- 情報収集:地域の介護サービス情報を事前に把握
- 味方を増やす:直属の上司だけでなく、人事部や同僚にも状況を共有する
4. 【注意点・デメリット】知っておくべきこと
利用時の注意点
制度利用時の主な注意点:
- 申請期限がある制度が多い:事前の準備が必要
- 所得保障が完全ではない:経済的計画が重要
- 職場復帰時の配慮:復帰後のサポート体制確認が必要
よくある勘違い
| 間違った思い込み | 正しい情報 |
|---|---|
| 「正社員しか使えない」 | パート・アルバイトでも条件を満たせば利用可能 |
| 「会社が小さいから制度がない」 | 法定制度は企業規模問わず適用 |
| 「介護が終わらないと復帰できない」 | 段階的な復帰も可能 |
デメリット・制限事項
主なデメリット:
- 収入減少の可能性
- キャリアへの影響
- 職場での立場への配慮が必要
制限事項:
- 利用期間の上限あり
- 申請条件が厳格な場合がある
- すべての企業で制度が充実しているわけではない
5. 【まとめ】今日から使えるビジネスケアラー支援策3つのポイント
ビジネスケアラー支援策を最大限活用するための重要なポイント:
- 早めの情報収集と相談 まずは自分の会社にどんなビジネスケアラー支援策があるか人事部に確認してください。同時に地域包括支援センターにも相談し、利用できる介護サービスや支援制度を把握しましょう。
- 支援制度を組み合わせて使う 介護休業、介護休暇、短時間勤務、フレックスタイムなど、複数のビジネスケアラー支援策を状況に応じて組み合わせることで、より柔軟な働き方が可能になります。
- 専門家との連携を大切にする ケアマネジャーや社会福祉士などの専門職と連携することで、最適な支援策を見つけることができます。一人で抱え込まず、チームで支える体制を作りましょう。
最後に
この記事でご紹介したビジネスケアラー支援策を活用すれば、仕事と介護を諦めることなく両立できる道が見えてきます。ぜひ今日から行動を起こしてみてください。
この記事が「仕事と介護の両立について知りたい」「ビジネスケアラー支援策を活用したい」という方の参考になれば嬉しいです。
あなたの体験も教えてください!
- 実際にビジネスケアラー支援策を利用された方の体験談
- 「こんなことで困っている」というお悩み
- 「この支援制度についてもっと詳しく知りたい」というリクエスト
コメントやメッセージでお聞かせください😊 一緒に「生きやすさ」を見つけていきましょう!
この記事が役に立ったら、ぜひSNSでシェアしてください!
参考文献・リンク
- 厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
- 経済産業省「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」
- 厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法の概要」