こんなお悩みありませんか?
- 自分の気持ちや困りごとを周りの人に理解してもらえない
- セルフアドボカシーって言葉は聞いたことあるけど、いつから始めたらいいか分からない
- 障害のある自分でも、きちんと意見を言えるようになりたい
この記事で分かること
✅ セルフアドボカシーの基本的な意味と重要性
✅ セルフアドボカシーをいつから始めるべきか
✅ 実際に始めるための具体的なステップと体験談
「初めてこのブログをお読みの方は、
**[【はじめまして】福祉のプロ×当事者が始める理由]**
で運営者の詳しいプロフィールと、なぜこのブログを始めたのかをご紹介しています。」
この記事を書いている人

福祉の専門職(社会福祉士・精神保健福祉士)で、発達障害の当事者でもあるバッキーが、専門知識と実体験の両方からセルフアドボカシー について分かりやすく解説します。
📂 カテゴリー別記事一覧
🏛️ 社会保障制度 | 💼 福祉のお仕事 | 🧠 障害と生きづらさ
※本記事は社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士・保育士の資格を持つ私の実体験や専門知識、福祉制度の理解に基づく情報提供です。医学的診断や治療の代替となるものではありません。
1. 【基本編】セルフアドボカシーとは?中学生でも分かる基礎知識
簡単に言うと、セルフアドボカシーとは「自分で自分を守る力」です
セルフアドボカシーとは、自分の権利や意見を自分自身で主張する能力のことです。
「アドボカシー(advocacy)」は「代弁・擁護」という意味で、「セルフ(self)」がつくことで「自分で自分を代弁する」ことを表しています。
📌 具体的には以下のような力を指します:
- 自分の気持ちや困りごとを言葉で説明する力
- 必要な支援やサービスを自分から求める力
- 嫌なことに対して「NO」と言える力
- 自分の権利について理解し、それを主張する力
なぜこの力が必要なの?
障害のある人は、これまで「支援される側」として扱われることが多く、自分の意見を言う機会が少ない環境にありました。
しかし、「自分のことは自分が一番よく分かっている」 という当たり前の事実に基づき、自分らしく生きるためには自分の意見を伝える力が不可欠です。
誰が身につけるべきなの?
- 障害のある子どもから大人まで、すべての人
- 障害の種類や程度に関係なく、誰でも習得可能
- 知的障害の方でも、その人なりの方法で身につけることができる
2. 【詳細編】セルフアドボカシーをいつから始める?具体的な手順
⏰ 答え:「今すぐ」始められます!
セルフアドボカシーは 「いつから始める」というよりも「今この瞬間から」 実践できるものです。
年代別おすすめスタート時期
| 年代 | 始めるタイミング | 具体的な取り組み |
|---|---|---|
| 幼児期(3-6歳) | 「好き・嫌い」を表現できるようになったら | 「いや」「だめ」を言う練習 |
| 学童期(6-12歳) | 学校生活で困りごとが出てきたら | 先生に「分からない」と伝える |
| 中高生(12-18歳) | 進路について考え始める時期 | 将来の希望を具体的に話す |
| 成人期(18歳以降) | いつでも | 職場や地域で自分の意見を伝える |
実践のステップ
ステップ1:自分を知る
- 自分の障害特性を理解する
- 得意なこと・苦手なことを整理する
- 必要な支援を具体的に考える
ステップ2:伝える練習をする
- 家族や友人など、安心できる人から始める
- 「私は○○が苦手なので、△△の方法でお願いします」のような具体的な表現を使う
- ロールプレイで練習する
ステップ3:実際の場面で使ってみる
- 学校や職場で小さなことから始める
- 「もう少しゆっくり説明してもらえますか?」など、シンプルな表現から
- うまくいかなくても諦めず、次の機会を待つ
💡ワンポイント解説
専門職として気づいたポイント: セルフアドボカシーは「完璧に主張すること」ではありません。「自分の気持ちを少しでも相手に伝えようとする」その姿勢こそが重要です。
当事者として感じたこと: 最初は勇気がいりますが、一度伝えることができると「あ、こんなに楽になるんだ」という実感が得られます。
3. 【体験談】実際に実践してみた体験
🌟当事者としての体験
障害者手帳取得後:いつから意識し始めたか
私がセルフアドボカシーを意識し始めたのは、社会に出てから「どうして自分は周りの人と同じようにできないんだろう」と悩み続け、最終的に「社会不適合者」だと感じて会社を退職し障害者手帳を取得した後でした。
きっかけとなった出来事:
手帳を取得した後就職について相談を受けていた時、担当医から⇩
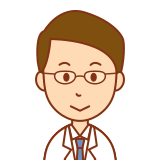
「あなたの困りごとを具体的に周りに伝えることが大切です」
今までは「迷惑をかけてはいけない」と我慢していましたが、新しく働き始めた職場で初めて上司に伝えました

「発達障害の特性で、複数の作業を同時に進めることが困難です。一つずつ優先順位を教えてもらえますか?」
結果:
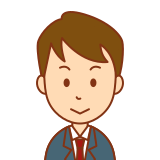
「そうなんですね。わかりました」
と上司は作業の進め方を一緒に工夫してくれるようになりました。手帳を取得してから、自分の特性を「欠点」ではなく「個性として伝えるべきこと」だと考えられるようになったんです。
【関連記事】障害者手帳を取得した体験談はこちらで詳しく書いています:
→ 【実体験】発達障害で障害者手帳を取得した理由とメリット5つ
社会人になってから:職場での実践
就職してからは、「いつから自分らしく働けるか」が大きな課題でした。
入社3ヶ月目に、上司との面談で「感覚過敏があるため、大きな音のする場所での作業が困難です。可能であれば静かな環境で作業させてもらえませんか?」と具体的に伝えました。
良かったこと:
- 集中できる環境で働けるようになった
- ストレスが大幅に減った
- 仕事の成果も向上した
【関連記事】感覚過敏についての詳しく説明しています。興味のある方はこちらもご覧ください
【感覚過敏】あなたは大丈夫?🔍感覚過敏の簡単チェック方法と対処法を当事者が解説
🌟支援者としての視点
現場でよく見る事例
支援の現場では「いつからセルフアドボカシーを教えるべきか」という質問をよく受けます。
印象的だった事例:
知的障害のある中学生が、特別支援学校で「僕は絵を描くのが好きです。将来は絵に関わる仕事がしたいです」とはっきり意見を言った場面を見ました。
利用者さんが躓きやすいポイント
- 「わがままを言ってはいけない」という思い込み
- 具体的に何を伝えたらいいか分からない
- 相手の反応を恐れてしまう
スムーズに進めるコツ
- 小さな成功体験を積み重ねる
- 「正解」を求めすぎない
- 支援者が見守りながら練習の機会を作る
4. 【注意点・デメリット】知っておくべきこと
⚠️ 注意点
すべての場面で主張する必要はない
セルフアドボカシーは「いつでも何でも主張すること」ではありません。時と場合を考えることも大切です。
相手の理解が得られないこともある
残念ながら、障害への理解がない相手もいます。そんな時は無理をせず、理解してくれる人や機関に相談しましょう。理解されないこと、これが本当に辛いです。
感情的になりすぎないよう注意
自分の気持ちを伝えることは大切ですが、感情的になりすぎると相手に伝わりにくくなります。
よくある勘違い
❌ 「セルフアドボカシー = 強く主張すること」
⭕ 正しくは:「自分の気持ちを適切に伝えること」
❌ 「一人で全部やらなければいけない」
⭕ 正しくは:「必要に応じて人の助けを借りてもOK」
デメリット・制限事項
- 身につけるまでに時間がかかることがある
- 周囲の理解や協力が必要
- 場面によっては使いにくいことがある
5. 【まとめ】セルフアドボカシーを今日から始める3つのポイント
🚀 実践ロードマップ
今日から始める3ステップ
【ステップ1】
🕐 「いつから」→「今から」
├─ 完璧なタイミングは存在しない
├─ 小さな実践から始める
└─ 継続が力になる
【ステップ2】
🎯 完璧主義を手放す
├─ うまく言えなくても大丈夫
├─ 相手に理解されなくても価値がある
└─ 伝えようとしたことが重要
【ステップ3】
🤝 仲間と一緒に成長
├─ 家族・友人のサポート
├─ 支援者との連携
└─ 当事者同士の支え合い
📈 継続的成長のサイクル
実践 → 振り返り → 改善 → 実践
↑ ↓
└── 仲間と支え合い ←──┘
1. 「いつから」ではなく「今から」始める
セルフアドボカシーに「早すぎる」「遅すぎる」はありません。今この瞬間から、小さなことでも自分の気持ちを伝える練習を始めてみましょう。
2. 完璧を求めず、小さな一歩から
「うまく言えなくても大丈夫」「相手に理解されなくても、伝えようとしたことが大切」という気持ちで取り組みましょう。
3. 支援者や仲間と一緒に学ぶ
一人で頑張る必要はありません。家族、友人、支援者、当事者同士で支え合いながら、セルフアドボカシーの力を育てていきましょう。
💬最後に
この記事が「セルフアドボカシー いつから始めたらいいのか分からない」という方の参考になれば嬉しいです。
あなたの体験も教えてください!
- 実際にセルフアドボカシーを実践された体験談
- 「こんなことで困っている」というお悩み
- 「この部分をもっと詳しく知りたい」というリクエスト
コメントやメッセージでお聞かせください😊 一緒に「生きやすさ」を見つけていきましょう!
「この記事が役に立ったら、ぜひSNSでシェアしてください!」


